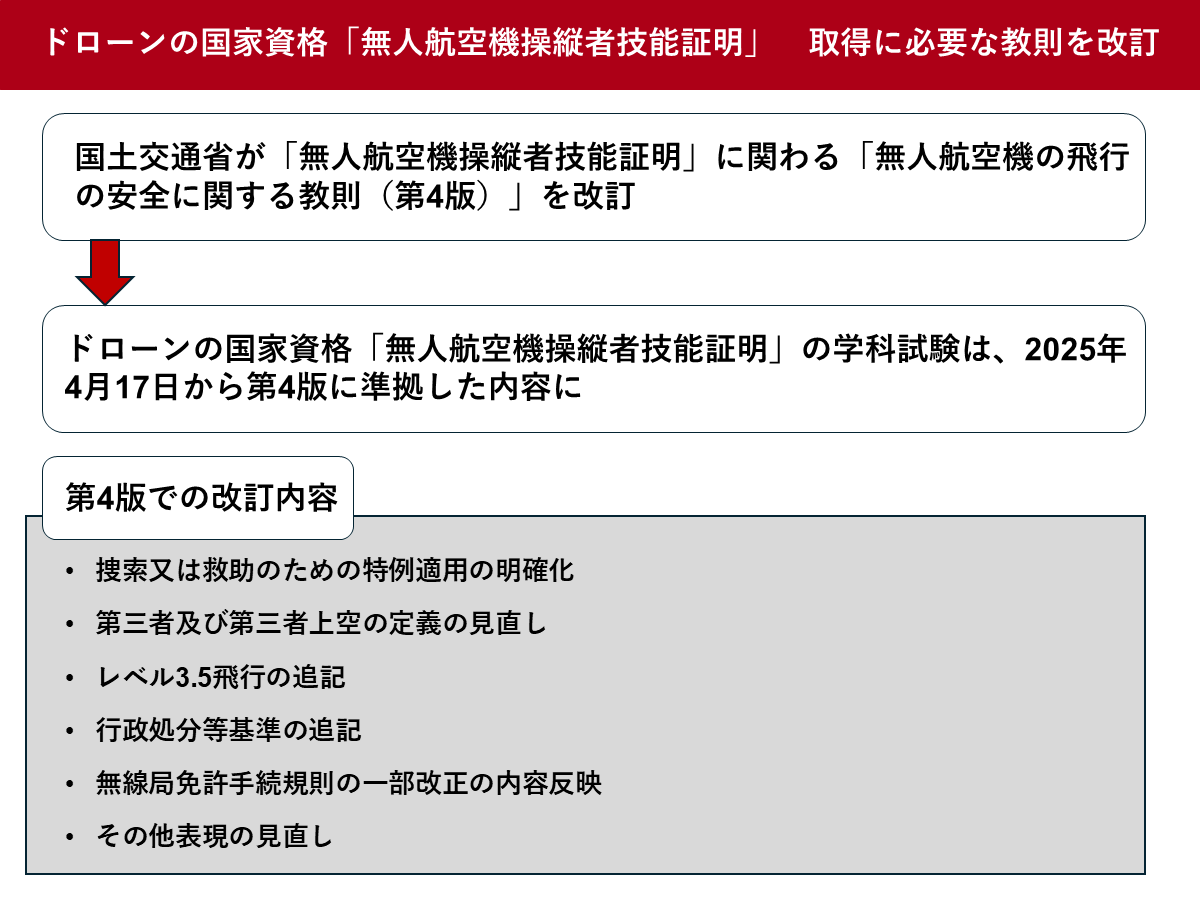トランプ大統領が発表した相互関税は、2025年4月2日にホワイトハウスで発表され、5日から一律10%の関税が発効、9日からは国ごとの追加関税が適用されるスケジュールです。
日本に対する24%の関税は、アメリカが日本による農産物(特にコメ)への高関税や自動車市場の非関税障壁を問題視した結果とされています。トランプ大統領は演説で、「アメリカは外国から搾取されてきた」と述べ、貿易赤字の解消と国内産業の復活を強調しました。
国際政治の観点からは、この関税政策はアメリカの覇権維持と経済的優位性の再確立を意図したものと解釈できます。第二次世界大戦後、アメリカは自由貿易を推進し、グローバル経済のルールメーカーとして君臨してきました。
しかし、トランプ政権は、こうした多国間主義を放棄し、一国主義的な「アメリカ第一主義」を前面に押し出しています。これは、中国やEUなどとの貿易摩擦を背景に、アメリカの経済的影響力をてこにした力による交渉を優先する戦略です。日本への関税も、同盟国であっても例外としない姿勢を示し、アメリカの利益を最優先するトランプ流のリアリズムを体現しています。
日米経済関係は、戦後一貫して緊密であり、日本にとってアメリカは最大の輸出市場です。とくに日本の対米自動車輸出は年間約137万台、約6兆円に上り、対米輸出全体の約30%を占め、日本経済の柱となっています。
トランプ関税が発動されれば、日本からの輸出品に24%の追加関税が課されることで、企業のコスト負担が増大し、価格競争力が低下する恐れがあります。内閣府の試算によれば、10%の一律関税で実質GDPが0.09%、自動車への25%関税で0.08%低下するとされています。
これにより、日本経済は短期的には打撃を受け、株価下落や円高圧力も予想されます。実際、4月3日の東京株式市場では、日経平均が一時1600円以上急落し、市場の懸念が顕在化しました。
一方で、アメリカ側にも影響は及びます。日本の自動車や部品はアメリカの製造業に深く組み込まれており、関税による価格上昇は消費者の負担増やサプライチェーンの混乱を招く可能性があります。
トランプ政権は国内製造業の復活を掲げますが、グローバル化が進んだ今日では、関税だけで産業を呼び戻すのは困難です。さらに、日本が報復関税を検討すれば、アメリカの農産物輸出(特に日本向けの4番目の市場)が打撃を受け、両国間の経済的緊張が高まるリスクもあります。
国際政治的には、この関税が日米同盟に与える影響も見逃せません。日米は安全保障面で協力関係にありますが、経済での対立が深まれば、政治的信頼にも影を落とす可能性があります。
トランプ大統領は、日本が防衛費増額や貿易赤字削減に応じなければさらなる圧力をかける姿勢を示唆しており、同盟関係が経済的交渉の道具として利用される懸念があります。これは、同盟国を「搾取者」とみなすトランプ大統領の認識が背景にあるといえるでしょう。
トランプ大統領の対日認識を読み解く
トランプ大統領の対日認識は、彼の演説や政策からいくつかの特徴が浮かび上がります。第一に、日本を「賢い交渉相手」と評価しつつ、不公平な貿易慣行への不満を繰り返し表明しています。
たとえば、「日本はアメリカ産コメに700%の関税をかけている」「トヨタは米国で100万台を売る」と批判し、日本の市場閉鎖性を問題視します。これは事実の一面を誇張したもので、コメへの高関税は例外的な措置であり、工業製品では日本がほぼゼロ関税である点は無視されています。
第二に、トランプ氏は日本を安全保障の「ただ乗り」とみなす傾向があります。第一次政権時から、日本や韓国に駐留米軍の経費負担増を求めてきた経緯があり、第二次政権でも同様の圧力が予想されます。2025年2月の日米首脳会談では、防衛費増額が議題に上り、経済と安全保障をリンクさせる姿勢が垣間見えました。
この認識は、日本がアメリカの保護に依存しつつ、経済では優位性を保つという不均衡への苛立ちを反映しています。
トランプ関税による日米関係の行方と日本の対応策
トランプ関税が日米関係に与える影響は、短期的には経済的混乱を招くものの、長期的には両国の交渉次第で収束する可能性があります。
日本としては、まず関税の影響を最小限に抑えるため、自動車の現地生産拡大や農産物市場の部分的開放を提案しつつ、アメリカの要求に応じる姿勢を見せることが考えられます。
同時に、インド太平洋戦略(FOIP)などを活用し、対中国での安全保障協力を強化することで、経済的圧力を相殺する戦略も有効かも知れません。
国際政治の観点からは、トランプ関税が自由貿易体制の終焉を示唆する一方で、新たな秩序形成の契機となる可能性もあります。
日本は、アメリカ依存からの脱却を図り、ASEANやEUとの経済連携を強化する「脱アメリカ」戦略を模索する必要もあるかもしれません。アフタートランプでも米国の保護主義が続くことになれば、世界経済の地域ブロック化はいっそう進み、日米関係も従来の枠組みを超えた再定義が求められるでしょう。
トランプ関税は、日米経済・貿易関係に大きな試練をもたらすと同時に、国際政治におけるアメリカの力の再構築を映し出しています。トランプ大統領の対日認識は、不満と交渉の余地が混在する複雑なものであり、日本はこれに柔軟かつ戦略的に対応することが求められます。
経済的打撃を最小限に抑えつつ、同盟関係を維持する道を模索する日本の外交手腕が、今後の行方を左右するでしょう。
ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。