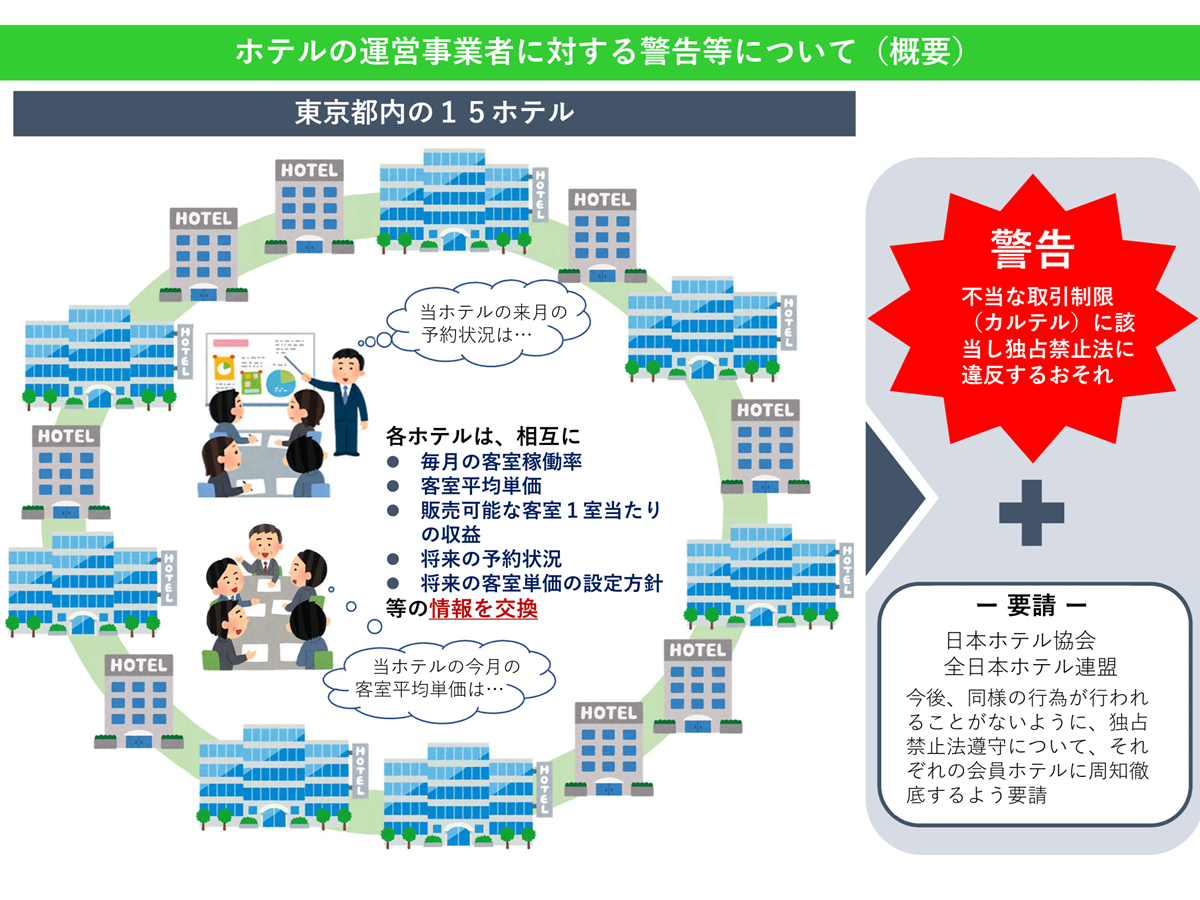このうち、「国境を封鎖し、移民の侵入を阻止する」「アメリカを圧倒的に世界最大のエネルギー生産国にする」「アウトソーシングを止め、米国を製造業の超大国にする」「男性を女性のスポーツから締め出す」「電気自動車の義務化を中止」といった20項目を「コア」に位置付けています。
公約は、関税により税収を増やす一方で、DEI(多様性・公正性・包括性)や環境分野、移民などに関する政府支出を削減し、労働者への減税などへの再配分に力を入れるという3つの基本方針で整理できます。
こうした政策を見ていくと、トランプ大統領が就任100日までに公表した政策は、追加関税や、DEI(多様性・公正性・包括性)などの政府支出の削減から始まっており、今後、「労働者のための大規模な減税、そしてチップに対する税金なし!」などという公約があるように、減税などの政策を進めていくことが予想できます。
ただし、すでに世界各国や各メディアは、トランプ氏の掲げる政策が正確な根拠にもとづかないと批判しているため、公約の妥当性には注意が必要です。それでも、トランプ大統領は今後もAgenda47の公約を実行する可能性があります。
日本経済へ想定される影響
Agenda47が実行された場合、日本経済は以下のような複合的な影響を受ける可能性があります。
まずは楽観的な視点に立てば、米国の化石燃料増産による原油価格が短期的に下がる可能性があります(4月の米原油指標のWTIは下がっていますが、これはトランプ関税による景気減速懸念だとみられています)。
このほか、米国内市場において、中国製品に代わる代替品として、特定の戦略分野で日本企業が市場シェアを広げる可能性があります。
一方のリスク要因としては、相互関税などの追加関税措置で、輸出コストが増加すること、グローバルサプライチェーンに組み込まれた日本企業の事業再編コストや地政学的・経済的な不確実性の増大、対米投資への審査強化などが挙げられます。
また、米国が気候変動対策を後退させることで、国内でも少しずつ進んできたESGへの取り組みや日本のグリーン技術への投資にも影響が出るかもしれません。
以下で具体的に整理していきます。
貿易政策の転換と保護主義の再燃
Agenda47は、貿易政策で保護主義的な色彩を一層強める方向性を示しています。公約では「アメリカの労働者を保護するための新たな貿易計画」として、すべての輸入品に対する「包括的な基準関税」の導入を提案していました。これが10%の追加関税につながっているとみられます。
さらに、「トランプ相互貿易法」を掲げ、米国の関税に対して相手国が同等の関税を撤廃するか、さもなくば米国が同等の関税を課すという「相互関税」につながる内容も含まれています。
中国の最恵国待遇(MFN)の取り消し方針も示しており、具体的には「電子機器から鉄鋼、医薬品に至るまで、あらゆる必須商品の中国からの輸入を段階的に廃止する4カ年計画を採用する。これには、中国が第三国を経由することで規制を回避できないようにするための強力な保護が含まれる」と記しています。
中国をサプライチェーンのハブとする日本企業にとって、部品調達の遅延やコスト増など間接的な影響を受ける可能性があります。
サプライチェーンの再編と生産国内回帰の圧力
Agenda47は、経済安全保障の観点から、中国への依存を脱却し、重要物資の生産を米国内に戻す「リショアリング」を強く推進する方針を示しています。特に、抗がん剤をはじめ、医薬品などの重要品目の国内生産回帰を目指すとしています。
このほかにも、「自動車産業を救うため、有害な規制を逆転させ、電気自動車義務化などをキャンセルし、中国製自動車の輸入を防ぐ」といったことを掲げています。重要なサプライチェーンをアメリカに回帰させ、国家安全保障と経済安定を確保し、雇用と賃金を創出するとしています。
グローバルに最適化されたサプライチェーンに深く組み込まれている日本の製造業(自動車、電機、化学など)にとって、米国市場でのシェアを維持するには、サプライチェーンの見直しや生産拠点の再配置を迫られる可能性があります。これには多大なコストと時間がかかり、企業の収益性を圧迫する要因となり得ます。
さらに、トランプ氏は「米国企業の対中投資を阻止し、中国による米国買収を阻止するための新たなルールを確立し、米国の利益に資する投資のみを許可する」という方針も掲げています。米国内への外国投資、特に戦略的に重要とみなされる分野への投資に対する審査が強化される可能性があります。
日本企業による対米投資も、より厳しくなるリスクがあり、サプライチェーンの分断と投資規制の強化は、日本企業のグローバル戦略の見直しにもつながるかもしれません。
エネルギー政策と気候変動への取り組みの後退
Agenda47は、「地球上で最も安価なエネルギーと電力を実現する」こと、および規制緩和を通じて「再びエネルギー自給国となる」ことを目標に掲げています。すでに「掘って掘って掘りまくれ」と化石燃料の石油と天然ガスを増産する方針を示しています。
しかし、このエネルギー政策は、気候変動対策やESG(環境・社会・ガバナンス)投資に対する後退と表裏一体です。Agenda47では、ESG投資を「詐欺的な金融スキーム」とし、エネルギー生産を妨げると見なされる環境規制の撤廃も示唆されています。
米国が国際的な気候変動対策の枠組みから距離を置く、あるいはESG原則を積極的に抑制するような動きを見せれば、地球温暖化対策に関する国際協調体制が揺らぐ可能性があります。
地政学的シフトと経済の安定性
米国の同盟へのコミットメントが、予測困難なものになるという認識が広まれば、東アジア地域の地政学的な不確実性は高まるかもしれません。
日米関税交渉のなかで、米国側は在日米軍の駐留費が高いことも論点の一つになっています。とくに、日本と経済的な結びつきの強い台湾政策についても注視が必要です。トランプ氏はかねてより、先端半導体産業を台湾から取り戻すこととと防衛費の大幅増を台湾に迫っているためです。
今後のトランプ政策の見通し
トランプ氏のAgenda47はあくまで、大統領選時点での公約であり、関税などをめぐる市場の混乱で政策の見直しを進めているなか、今後、実際の政策としてどの程度、どのように実行されるかは不透明です。
しかし、日本の政府および産業界は、米国の政治・政策動向を綿密に注視し、様々なシナリオを想定した上で、サプライチェーンの強靭化、市場の多様化、技術開発戦略の見直し、そして同盟国やパートナー国との連携強化といった、先を見据えた対応策を準備・検討していく必要があります。
ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。