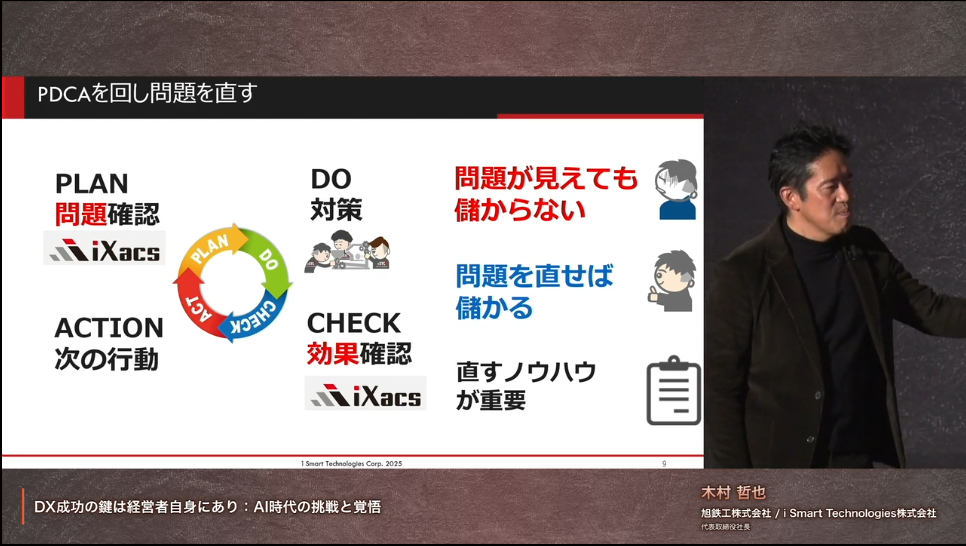「八女提灯」は、お盆の時期に仏壇や玄関に飾る提灯として広く知られています。灯りを囲むように袋状になった「火袋」(ひぶくろ)と呼ばれる部分に、細い竹ひご(近年はワイヤーも使用)と薄い和紙を使い、花や風景などの彩色画が描かれているのが特徴です。八女は古来から和紙の生産地で、竹林も多かったことから、江戸時代後期から提灯づくりが盛んでした。
入江さんの父・哲也さんはかつて、本業の農業のかたわら提灯メーカーの火袋づくりの下請けを内職で行っていました。そこから独立し、1980年にシラキ工芸を創業します。創業の地となった八女市立花町白木の地名にあやかった屋号です。
当時は「火袋をつくればすぐ売れる時代」(入江さん)。哲也さんが夜遅くまで一生懸命働いていたことを入江さんはよく覚えているそうです。そして「いつか自分が継ぐことになるんだろうな」とぼんやり思っていました。ただ哲也さんから後継ぎについて話題にされたことはなく、高校を卒業すると、福岡市内の雑貨店に就職しました。
20歳の時に結婚して長女が生まれると、もっと稼ぎたいと思うようになり、哲也さんに頼んで家業入りします。理由は「よく売れてシラキ工芸が儲かっているように見えた」(入江さん)から。入江さんの妻も加わり、一家3人の体制となりました。
21歳で次女も生まれ、入江さんは家計を支えるために一生懸命働きました。ただ、当時は火袋の絵付けや漆塗りなどの工程の大半を下請けの職人に依頼する分業制。外注費がかさみ、入江さん夫婦が受け取っていた給料は多くありませんでした。
また洋室がメインの家が増えて、仏壇を置ける空間が一般家庭になくなってきたため、提灯の市場も少しずつ縮小していたといいます。周囲でも廃業する業者が出始めていました。
自分の手取りを増やし、事業形態も変えなくてはいけない――。そう考えた入江さんは、家業入りから4年ほどして哲也さんに「経営を代わってくれ」と頼みます。その頃になるとメーカーや問屋など取引先との窓口役を担い、信頼関係も深くなっていたため、「自分が経営する方が売り上げも増やせそうだ」とも考えたのです。
当時哲也さんは50代半ばでしたが、農業に戻りたいという気持ちもあったようで、1998年にシラキ工芸の経営は入江さんに完全に交代します。それ以降、哲也さんが経営に口出しすることはほとんどありませんでした。
 入江さんは20代半ばで経営を引き継ぎました
入江さんは20代半ばで経営を引き継ぎました
入江さんがまず手がけたのは事業規模の拡大でした。
当時のシラキ工芸はメーカーからの発注を受けて、企画やデザイン、受発注管理を担い、実際の火袋づくりは下請けの職人が手がけていました。
代替わり前は家族3人と職人約80人でしたが、徐々に約150人に業務委託できる体制にしました。入江さんがメーカーや問屋などの対応に、入江さんの妻が受発注管理や事務作業などに集中できるようにしたのです。
約1億3千万円がピークだった年間売上高も、入江さんが30歳になる頃には最大約1億7千万円まで増えました。
職人不足で外注依存に課題感
規模はそれなりに拡大できたものの、製作体制は決して盤石ではありません。課題の一つは、熟練の職人が高齢化で少しずつ減っていたことでした。当時は八女の職人の多くが60~70代で、若手はあまり育っていなかったのです。
もう一つ課題がありました。シラキ工芸に限らず八女の提灯業界の大半は職人への外注で製作を依存していた一方、ほとんどの職人は農業などの合間に提灯を作っていました。悪天候による農作業の遅れなどがあれば提灯づくりの工程にも影響し、結果的に納期遅延が頻発していたのです。
入江さんは外注ではなく自前で若い職人を育てたいという気持ちが強くなりました。伝統の提灯づくりを未来へ承継することへの課題感も抱いていました。
そこで地元の若者を正社員として採用し、自ら職人として育成することに。個人事業だったシラキ工芸も2004年、法人化(有限会社)しました。
 シラキ工芸では火袋の絵付けなどの作業を若手職人が担っています
シラキ工芸では火袋の絵付けなどの作業を若手職人が担っています
自由に製作できる職場環境を
同時期に知人の紹介やハローワークなどを通じて24~25歳の数人を雇用できました。事業所も移転し、銀行融資を受けて新社屋の隣に工房も建てました。
技術承継に理解がある熟練の職人に頼み、指導してもらいました。「多くの職人さんにとって孫のような年代の若者ばかり。かわいがってもらいながら丁寧に教えてもらえました」と振り返ります。
入江さんは、社員らがある程度技術を覚えたら「あとは任せるから好きなようにやっていい」と伝え、自由な雰囲気で製作ができる環境づくりに努めました。工房は全室を冷暖房完備にして、楽に作業ができるよう、オリジナルのTシャツやパーカーなどを支給しました。
特に小さな子どもがいる女性でも働きやすいよう、社会保険労務士と相談しながら、勤務時間を柔軟に設定したり在宅で仕事ができるようにしたりしました。
中には技術の習得がうまくいかないなどの理由で早期に退職する社員もいました。それでも入江さんは一般的に厳しいイメージの「職人の世界」とは異なる、働きやすい職場にして雇用を確保することを優先しました。
「そもそも盆に提灯を飾るといった風習も廃れつつありました。伝統工芸品であっても新しい時代の需要を理解できる若手職人に長く働いてもらって、技術を次に継いでもらわないと、会社も業界もいずれ存続できなくなると考えました」
家族経営だったシラキ工芸も現在の社員数は7人となり、うち20-30代は6人です。
 提灯に絵を描く若手職人
提灯に絵を描く若手職人
下請けからの脱却を図る
若手職人が育ち、外注に頼らない安定的な製作体制が整うと、メーカーなどからのさまざまな注文にも正確かつ迅速に応えられるようになり、発注量も増えていきました。
そこで入江さんは、新たな施策に取り組み始めます。
シラキ工芸はメーカーや問屋からすると「下請け」の立場。価格交渉で値引きを要請されるなど、経営が安定しませんでした。どれだけ高い品質の火袋をつくっても、「シラキ工芸」の名が記されるわけでもなく、若手職人のモチベーションが高まらないという課題もありました。
そこで入江さんは、若手職人らと話し合いを重ね、自社ブランドを開発して下請けからの脱却を試みます。そして2019年に完成したのが、どんなインテリアにも合わせて使える提灯シリーズ「cocolan」(ココラン)でした。
 cocolanシリーズ(シラキ工芸提供)
cocolanシリーズ(シラキ工芸提供)
提灯の主な発注元である仏壇業界では、和室の小型化や和室自体がない家に合わせて、コンパクトな仏壇や和室以外にも置ける仏壇などが増えていました。一方で盆提灯はまだ従来の大きなサイズが多く、現代のライフスタイルに適応していない状況でした。
cocolanは、若手社員からの「コンパクトなサイズで現代風の仏壇にもマッチし、普段使いもできる提灯をつくろう」という意見を元に開発されました。
製作には八女提灯の伝統工芸の技を注ぎ込みました。ただ、これまでの提灯の火袋より木型が小さいため、若手社員がCADを学ぶところから挑戦し、図面や3Dデータを作成して量産できるようになりました。入江さんは「若い社員は入社するまで伝統的な盆提灯に触れる機会が少なかったので、絵柄やデザインの発想が面白かったです」と話します。
 cocolanシリーズはインテリアとしても広がっています
cocolanシリーズはインテリアとしても広がっています
cocolan完成後、当初は取引のあったメーカーや問屋に配慮して新たな販路は積極的に開拓せず、若手社員が運用するインスタグラムでPRしたり、無料でプレスリリースを出したりするだけでした。それでも、業界最大手の仏壇販売店から、問い合わせが寄せられました。その後商談も順調に進み、直接取引が実現したのです。
cocolanは一気に成長し、今ではシラキ工芸の3分の1ほどの売り上げを占める商品となりました。
「自社ブランドとして、直接消費者に販売できるメーカーに卸しているため利益率も高く、経営の安定に大きく貢献しました。これも若手社員を採用して育成した成果の一つだと思います」
 cocolanシリーズはシラキ工芸の看板商品となりました(シラキ工芸提供)
cocolanシリーズはシラキ工芸の看板商品となりました(シラキ工芸提供)
中川政七商店のコンサルで新商品
次に若手社員主導で開発したのが、リビングなどで使えるポータブルライトの「TORCHIN」です。cocolanの製法を応用。現代風にLEDライトやタッチセンサーなどを盛り込み、USBケーブルで充電できてどこでも持ち運べる仕様にしました。コンセプトは「はこぶ、ともす、ほっとする」です。
 TORCHINシリーズ(シラキ工芸提供)
TORCHINシリーズ(シラキ工芸提供)
入江さんは開発にあたって、伝統工芸品の産地再生に取り組む事業者を支援する福岡県の「伝統的工芸品リーディングカンパニー創出事業」に応募し、2回目で採択されました。
県から業務委託された中川政七商店にコンサルティングしてもらって完成しました。デザインやコンセプトづくりだけでなく、完成後のブランディングでも支援を受け、中川政七商店のオンラインショップでも販売されています。
「コンサルティングの過程で、シラキ工芸の強みや『どうありたいか』を言語化するところから始めました。提灯の歴史を苦労して調べると、自分たちが目指す方向性が明確になっていきました。その結果、自社のビジョンが固まり、会社や仕事が『生き様』のようになりました」
2024年夏から発売を始めたTORCHINの売上高は、同年11月までに1500万円ほどですが、cocolanに次ぐ自社ブランドに育てたいと入江さんは意気込んでいます。
シラキ工芸が下請けだった時代には、年間約20万個の火袋を製作していました。近年はcocolanやTORCHINなどと合わせた製作数は年間約10万個ほど。それでも売上高は、下請け時代のピーク時の約1億7千万円から、1.7倍の約2億9千万円(2023年9月期)になりました。利益率も大きく上昇しています。
海外展開や実店舗にも挑戦
シラキ工芸は、2024年から欧州など海外向けの販売も始めました。まだ100万円台の売り上げですが、今後も海外の販路強化に取り組む方針です。2025年1月にはフランスの展示会に出展。近い将来、ドイツやイタリアにも進出したいと望んでいます。
 シラキ工芸の実店舗「ちょうちん堂」(シラキ工芸提供)
シラキ工芸の実店舗「ちょうちん堂」(シラキ工芸提供)
これに先立つ2022年には、初めての実店舗「ちょうちん堂」を八女市内に開店しました。2026年度にも完成する福岡空港の国内線ターミナルの複合施設内にも出店する計画を進めています。
 入江さんは海外進出や直営店の拡大などの道筋を描いています
入江さんは海外進出や直営店の拡大などの道筋を描いています
コロナ禍の後、お盆に帰省して先祖に思いをはせる機会が減り、盆提灯そのものは今後も厳しい状況が続くと予測しています。それでも入江さんは挑み続けるつもりです。
「現代の空間と生活習慣に合った提灯に進化させるため、若い職人とともに技術を承継して高品質な提灯をつくり続け、新しい時代のトレンドやニーズをしっかり採り入れていきたいと思います」