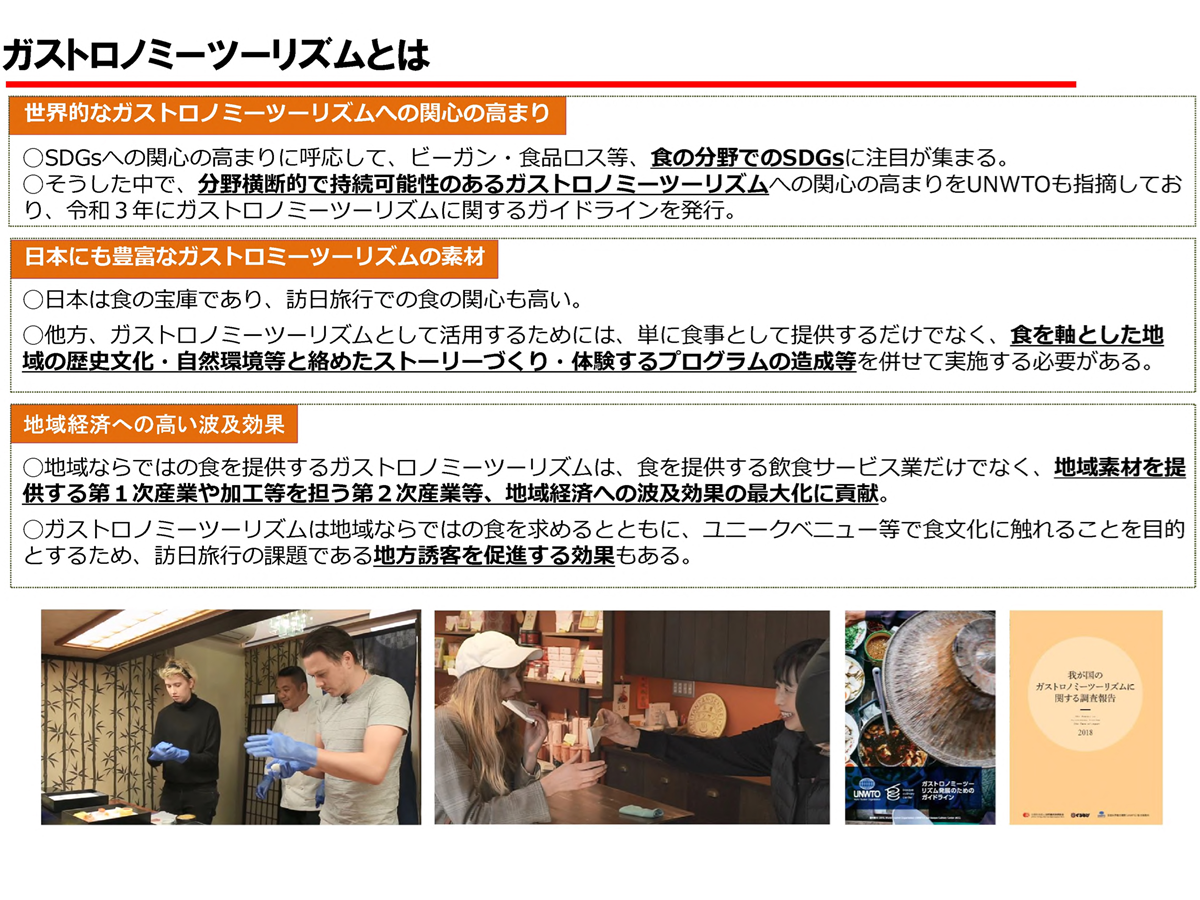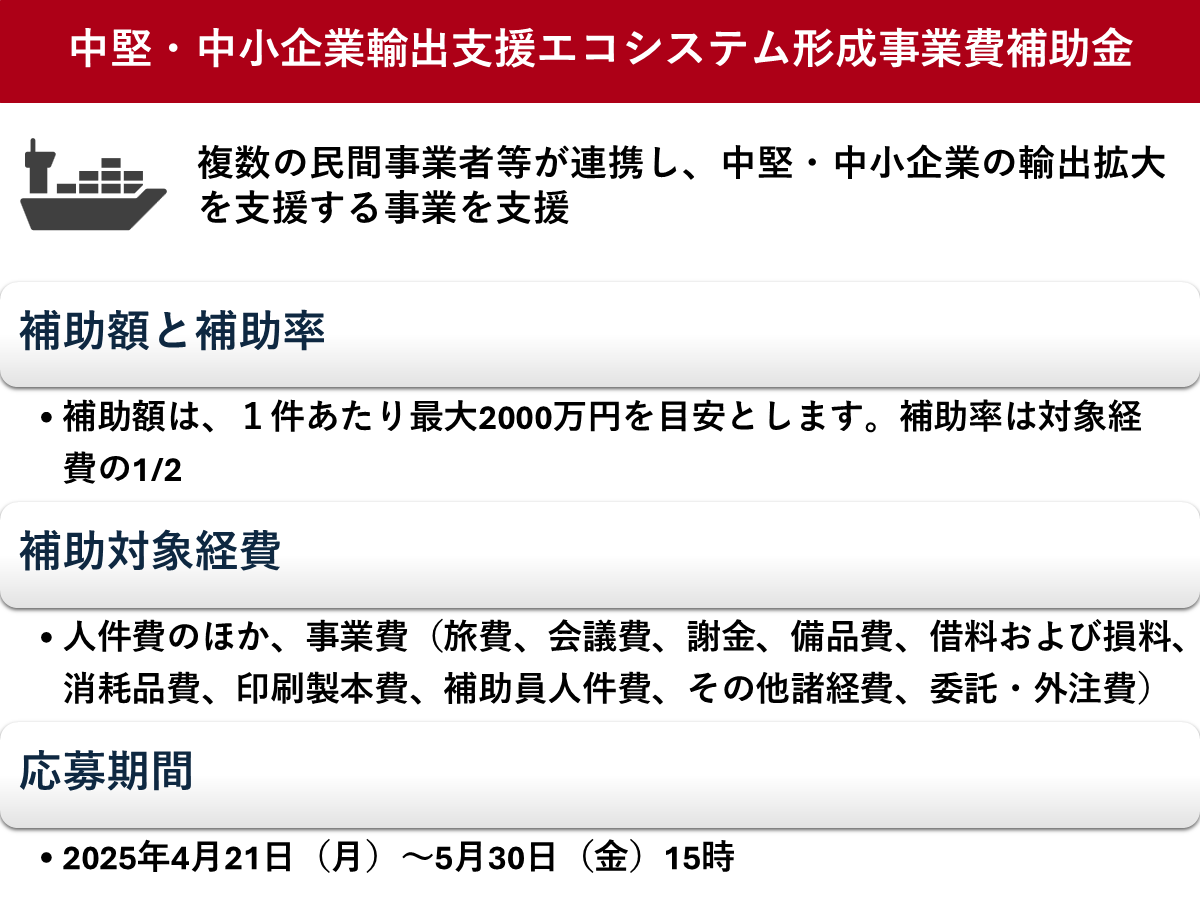ガストロノミーツーリズムとは 観光庁が2025年度事業の地域公募開始
杉本崇
(最終更新:)
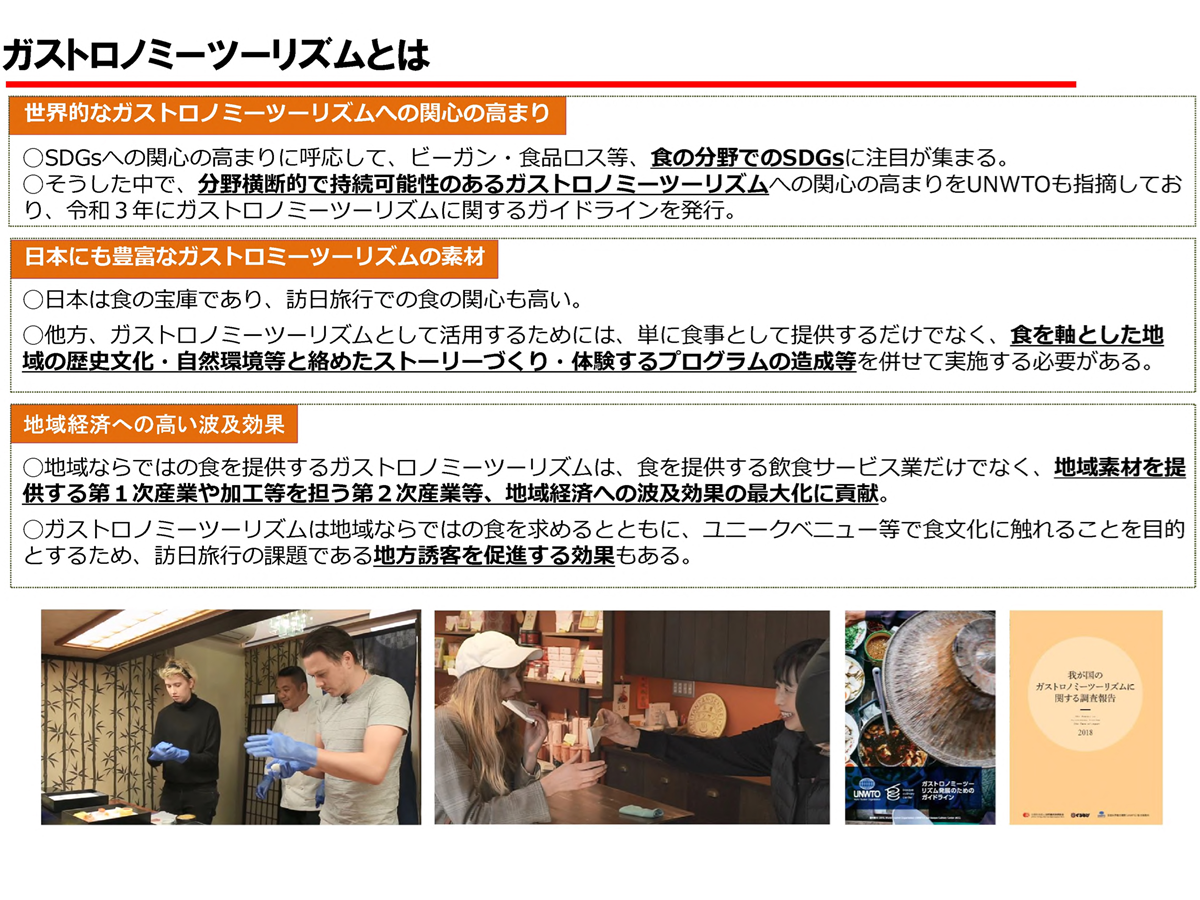 ガストロノミーツーリズムの概要(観光庁の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/shohikakudai/shokuzai/gastronomy.html)
ガストロノミーツーリズムの概要(観光庁の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/shohikakudai/shokuzai/gastronomy.html)
観光庁によると、ガストロノミーツーリズムとは、その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を楽しみ、食文化に触れることを目的としたツーリズムのことを指します。観光庁は、地域の「食」の力を最大限に活用し、食文化を目的とした観光「ガストロノミーツーリズム」を推進する事業の地域公募を開始しました。この事業は、地域の魅力を高め、観光分野全体の経済波及効果を地域全体に広げることを目指しています。公募期間は、2025年5月30日~6月30日となっています。
ガストロノミーツーリズムとは
観光庁の公式サイトによると、SDGsへの関心の高まりに呼応して、ビーガン·食品ロス等、食の分野でのSDGsに注目が集まるなか、世界観光機関(UNWTO)もガストロノミーツーリズムのガイドラインを出しています。
ガイドラインのポイントは以下の通りです。
- 透明性があり、参加型で、リーダーシップを促進するガバナンス(統治)モデルを推進する
- 地域のガストロノミーを文化遺産として認識する
- 観光客を受け入れるシナリオ、環境、場所及び体制を改善する
- 地域に内在するガストロノミーに関する商品・体験を、創造・開発する
- 関係者全員の知識、能力開発、革新、連携に基づき、バリューチェーンにおける競争力を強化する
- ガストロノミーに関心を有する観光客の特徴を把握するため、データ収集の仕組みを開発し、地域の状況を分析する
- 地域のガストロノミーについて、ブランドとして信頼できる本物のストーリーを展開する(食のブランド化)
- 関係者全員が参加し、ガストロノミーツーリズムの市場開拓を推進・支援する計画を策定する(食のマーケティング)
- ガストロノミーツーリズム発展の原動力として、テクノロジーを最大限に活用する
- 地域における持続可能性やSDGsへの貢献に向けた取組を進めるための手法としてガストロノミーツーリズムを推進する
日本でも、食をフックとした観光振興に取り組みたい地域が多い一方、地域の歴史・文化・自然環境等と関連付けた本質的な体験としての昇華や、関連産業と一体となった体制構築を通じて地域経済への経済波及効果を生み出している事例はまだ少ないのが現状です。
そこで、観光庁は、地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、農業・漁業・飲食業・宿泊業等の様々な関係団体等が連携し、地域の食資源(農作物、水産物、畜産物、酒、加工品・調味料等)を中心に、地域独自の歴史・文化・自然環境といった地域資源を主な対象として、ガストロノミーツーリズムに取り組むことを支援します。
「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進事業
この事業は、地方公共団体・観光地域づくり法人(DMO)・民間事業者等が、「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズムを体験するために必要な施設等の整備・改修や設備・備品の購入、コンテンツ造成、販路の形成等に係る経費の一部を国が補助する事業です。
応募申請の概要
事業実施者の対象となる申請者は、観光振興事業費補助金(「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進事業)の交付を受けて補助対象事業を実施する者であり、地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、民間事業者等が該当します。
補助対象経費
「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進のための、地域ならではの高品質なサービス・体験を提供する、施設整備やコンテンツ造成、販売経路の形成等
補助率は1/2以内とし、補助金の額は1事業計画あたり2500万円を上限とします。(金額の下限は特に設けません)
歴史的建造物、文化施設や公的空間等の特別な施設等の整備・改修費や、ユニークベニュー活用に係る特別な空間演出等を必要とする設備・備品の購入、体験コンテンツ造成に要する経費、販路形成に係る旅行商品の造成や各種情報発信等に要する経費とします。
対象経費については、採択件数の多寡や採択過程における選定委員による書面審査やヒアリングの結果等を踏まえた上で、金額を調整します。
公募要領・問い合わせ先
事業に関する質問は、電子メールでのみ受け付けられます。公募要領や問い合わせ先は観光庁の公式サイトへ。
経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
-
杉本崇
ツギノジダイ編集長
1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。
杉本崇の記事を読む