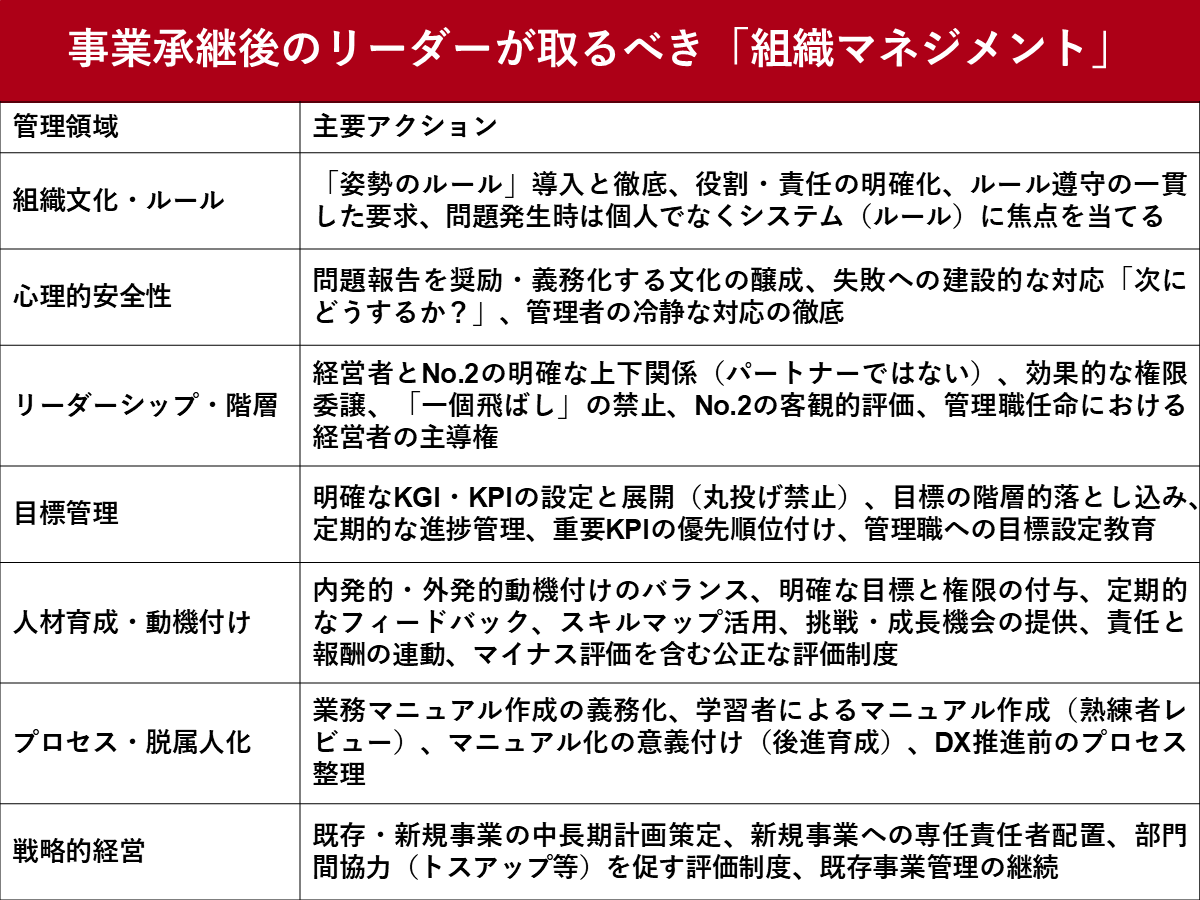ティール組織とは、2014年に組織コンサルタントのフレデリック・ラルー氏が、著書「Reinventing Organizations」で紹介した概念です。権力を持った社員が存在せず、各社員が自らの担当範囲のなかで経営に関わる重要な意思決定をしていく体制を指します。
ラルー氏は、組織が成熟するにつれ、超トップダウンの状態から社員一人ひとりが意思決定できる状態まで進化していくと説き、その過程をレッド、アンバー(琥珀色)、オレンジ、グリーン、ティール(青緑色)の五つに分類しました。日本では、同書の邦訳版「ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現」(英治出版)が18年に出版され、それに合わせて解説本も数多く発売された結果、ティール組織に注目が集まり始めました。
ティール組織は、社員が主体的に動く結果、素早い意思決定が可能になるというメリットがあるかもしれません。しかし、日本の中小企業は安易にティール組織を目指すべきではないと、筆者が考えます。
前提として、日本と海外では文化や制度が全く違います。例えば、解雇に関するルールの違いはその象徴の一つです。米国をはじめとした海外と比べて、日本の会社は、簡単に社員を解雇しづらいルールになっています。
もし、解雇されない前提で経営の根幹に関わる意思決定権だけを与えられたら、どうなるでしょうか。社員は自らの立場を踏み越えて行動する恐れがあります。これが過ぎれば、会社が傾くのは時間の問題です。逆説的に言えば、社員の自主性を重んじるティール組織を実践するためには、いつでも社員を解雇できるという欧米流の厳しいルールが不可欠なのです。
それは、経営者と同じレベルの意思決定を次々こなす社員が複数人必要になることです。経験が浅い社員にそんな重責を与えるのは難しく、労働人口の減少が叫ばれ、人材獲得競争の激しい日本で、優秀な人材を見つけ出すのは至難の業になります。
経営者やリーダーは、部下の役割を明確にして、ルールを定める、すなわち「決める役割」が最も重要です。しかし、安易にティール組織に飛びつくのは、それを放棄することにもつながりかねません。
動画配信世界大手ネットフリックスの体制について記した「NO RULES 世界一『自由』な会社、NETFLIX」(日本経済新聞出版)という本があります。それによると、同社はタイトルの通り社内ルールがなく、休暇は自由に取れる。上下関係もなく、誰でも役員に物申してよいとあります。まさにティール組織の典型です。
その一方、採用基準が極めて高く、最初から優秀なメンバーしかいないことが前提です。そして、成績が芳しくない社員には去ってもらう。だからこそティール組織が成り立つのです。
ティール組織を望むのは、経営者ではなく管理職や末端の社員でしょう。そういう人からすれば、上司に一方的に指示されるのではなく自分の思い通りに行動しやすいティール組織を理想とするはずです。
しかし、採用に悩む中小企業が安易にティール組織化に挑み、「自由な働き方ができる」と訴えて人材を集めようとしたら悲惨な目に遭います。
ティール組織に限らず、海外から来たマネジメント理論の運用を試みるときには注意してください。日本と海外の企業形態や組織文化の違いをよく調べ、本当にうまくいくのか、立ち止まって考えるようにしましょう。
社員の不満が続出したIT企業
個人の意見を尊重するという点において、フラット型組織を好む日本の経営者も少なくありません。経営者以外の全社員を同列の立場に置き、経営者は社員の自主性を重んじるという形で、「好きにやってよいから、アイデアをどんどん出しなさい」と言うケースもあるでしょう。
発想はティール組織に近いですが、ここには大きな落とし穴が隠れています。
あるIT系の中小企業で実際にあった話をご紹介します。その会社では、経営者が、「どんどんアイデアを出して、好きにやってください」と社員に発破をかけていました。そう言われた社員も最初は楽しく、「いい会社だな」と思っていたそうです。
しかし、それも最初だけ。社員に話を聞くと、「私は一生懸命やっているのに社長は全然評価してくれない。いくらアイデアを出してもどんどん却下される」、「何をしたらいいかが分からない。はっきりさせてほしい」という不満が続出しました。
本当のところ、経営者はフラットな組織をうたいつつも、結局、最後は自分が何もかも決めたいのです。それなのに「アイデアを出しなさい」と言っているのは、社員の役割をきちんと決められないからです。このように、フラット型組織を掲げても、実態は社員は苦しみ、経営者だけが満足しているというケースは少なくないと考えます。
他にも、組織図上は階層があっても、実際は経営者が全社員に直接指示を出すような「フラット型組織」も珍しくありません。経営者が何もかも自分で決めないと気が済まない反面、中間管理職は自らがすべきマネジメントについて理解せず、プレーヤー時代と同じように働いてしまうために、結果として悪い意味でフラットな組織になってしまうのです。
自由な発想を生かすルールと役割
筆者が考える理想的な組織体制は、社内にピラミッド型の階層を設け、トップである経営者の指示が中間管理職を通じて現場の社員にまでスッと落ちていき、現場で起きている情報が即座に経営者まで吸い上げられる状態です。
そのために中小企業経営者の皆様は、ルールと組織図、ポジションごとの役割を明確に設定しましょう。その上で、各管理職には部下の仕事のやり方を管理するのではなく、結果だけを見るように指示してください。
つまり、社員の自由は、あらかじめ定めたルールや役割の範囲内で認めるということです。そうすれば、社員は自由な発想を生かしながら、組織が望む方向へと努力してくれます。責任が明確で、その範囲内で意思決定する。この点については、ティール組織の要素が入っていると言えます。
かつての町工場とティール組織
本来、ある目的を達成するために誕生した組織は自ずとピラミッド型になるはずと考えます。例えば、生死を争う軍隊がティール組織になるでしょうか。軍隊は指揮命令系統が整っていなければ、下手すれば隊員の死につながりかねません。そして、隊員を守るための厳格なルールもあります。
これは、ビジネスの世界にも当てはまります。経営理念の下に原則、一人の経営者がいて、だんだん一人では仕事をこなせなくなってきたタイミングで社員を増やし、その過程でマネジメントをスムーズにするために管理職が必要になり、階層が生まれます。経営者が新入社員に自分と同じ役割を任せるはずはありません。
かつて、日本に数多く存在した町工場は、あるいはティール組織と呼べたかもしれません。類まれな技術を持った職人たちがただひたすら制作に打ち込み、経営者も職人たちのすごさを分かっているからこそ任せて、結果として高い品質の製品が生まれ、世の中に選ばれる会社となっていきました。
ただし、現代の中小規模の製造会社が同じような方針を掲げても、うまくいかないことが多いでしょう。昔は一度入社した会社には定年まで勤めるのが当たり前で、それゆえに職人の技術は自然と若い世代へ受け継がれていきました。
しかし、少子高齢化が進んだ今は違います。より良い待遇を求めて、転職は一般的になり、技術の伝承も期待できません。
経営者に求められているのは、時代に合わせながらも確固たる経営方針を打ち出すことではないでしょうか。本記事がその助けになれば幸いです。
畠中光成さん
識学上席コンサルタント・コンサルティング部 課長
関西学院大学法学部を卒業。松下政経塾を経て、衆議院議員を経験。議院運営委員会理事、憲法審査会幹事、国家安全保障に関する特別委員会委員などを歴任。おもに議員の身分に関わるルールや、安全保障政策を策定。民間企業では明治安田生命、リクルートに在籍。会社経営も経験。
(※構成・平沢元嗣)
ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。