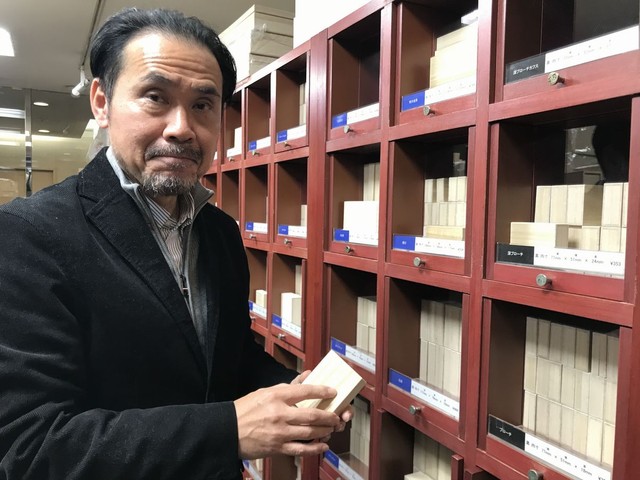箱義桐箱店の名で法人化したのは、4代目の戸張常義さん。常義さんは丁稚の一人で、その仕事ぶりが買われて3代目の長女と結婚します。4代目候補の長男が戦死し、後を継ぐことになりました。
「孫の自分がいうのもなんですが、その手並みは確かだったようです。宮内庁からも声がかかるくらいですからね。使いに出された親父は美智子さま(現・上皇后さま)の還啓に出くわしたことがあったとか。職員の列に加わって敬礼したそうです」
顧客リストには宮内庁のほか、徳川ミュージアム、東京藝術大学、東京国立博物館、町田市立博物館、日本橋高島屋、上野松坂屋が名を連ねます。着物や刀、宝飾品を納める特注品をつくってきました。
高度経済成長期には会津や岩手に並ぶ桐の産地、広島とのパイプをつくり、量産体制も構築します。量産品は北は北海道から南は九州まで、3千を超える取引先があります。
現在その販路には直営店が加わり、総勢15人の社員で切り盛りしています。
 箱義桐箱店の本社(箱義桐箱店提供)
箱義桐箱店の本社(箱義桐箱店提供)
億単位の借金を抱えて社長に
小学校の文集に「日本一の桐箱屋になる」と書いた戸張さんは初志貫徹、1996年に家業入りします。
「社会人としての基礎体力をつけるため、まずは宝石会社のナガホリで5年ほど働きました。そのころから伝統工芸は厳しい戦いになると感じていました。顧客商売だけでは尻すぼみになる。継ぐ以上は営業のスキルを身につけて売り先を広げなければならない。宝石業界を選んだのはいずれうちのお客さまになる可能性があるからでした」
ナガホリは一代で上場した会社だけあって、その5年は目の回るような忙しさだったそうです。たいへんだったけれど、すべては将来の自分の糧になる――。そう考える戸張さんには、そんな環境をどこか楽しんでいるところがありました。
「家業に戻ったわたしは新規の取引をとんとん拍子で決めていきます。順風満帆を絵に描いたような船出でしたが、その船はなんの前触れもなく暗礁に乗り上げました。結論のみ述べれば、わたしは2003年、36歳の若さで社長に就任し、そして億単位の借金を抱えることになったのです」
戸張さんは返済計画を立てるべく、メーンバンクを変更します。そのやりとりは「半沢直樹」さながらでした。「代表に就任して最初の2年ほどの記憶は抜け落ちています。年明けの発熱にも長いこと悩まされました。無事年が越せて気が緩んだんでしょう」
祖父が築いた信用の重み
返済の目処をつけた戸張さんはそれまで縁のなかった業界にも手をつけます。それがインペリアル・エンタープライズをはじめとした通販会社でした。
「通販は高価な品を扱っていますから桐箱の需要があると踏みました。本来ターゲットにすべきは、通販に卸しているブランドやメーカーです。門前払いされてもおかしくないところですが、通販主体の企画などもあり、なんやかんやと声をかけていただけることになりました」
そのひとつが、全長2メートルに及ぶ戦艦大和の模型を飾る台座をつくってほしいというもの。一艦100万円を超えるその模型は飛ぶように売れました。
 右側の額の写真が4代目の戸張常義さん、左側の額が桐でつくった菊の御紋
右側の額の写真が4代目の戸張常義さん、左側の額が桐でつくった菊の御紋
飛び込み営業では、祖父が築いてきた信用の重みを感じることになりました。伝統工芸の工房や店をまわると、彼らは決まって仕事の手を休め、リーフレットを受けとりました。「箱義かい、知っているよ」といって。
重鎮が集まる組合の会合も祖父のおかげで乗り切れました。30代の戸張さんにとっては気後れのする場でしたが、みな口々に『きみのおじいさんには世話になった』といい、その輪に加えてくれたそうです。
「祖父は長男だったわたしを、ひときわかわいがりました。棟梁と呼ばれ、『棟梁ならみなの面倒をみるもんだ』と言い含められました。祖父はその通りに生きた人だった。祖父の背中は、わたしの行動指針になっています」
製作所に示す「大店の了見」
箱義桐箱店の生産は、特注品を祖父の弟弟子、量産品を迫田製作所(広島県福山市)に委ねています。
 特注品の製造は4代目の弟弟子が引き継いでいます(箱義桐箱店提供)
特注品の製造は4代目の弟弟子が引き継いでいます(箱義桐箱店提供)
「当社は1970年、広島の工場を傘下に収めて大量生産の基盤を固めましたが、わたしの代には工場としての体をなさなくなっていました。身内の恥をさらすようで恥ずかしいのですが、自社工場であることの甘えや高齢化などのさまざまな要素が重なったためです。迫田製作所から相談を受けたのはそんなタイミングでした」
聞けば息子も家業入りし、なんとしても会社を残さなければならないといいます。戸張さんはその真剣な眼差しに応えるべく、徐々に生産をシフトしていきました。
「やるからにはがっぷり四つで向き合いたいと伝えました。口でいうだけなら簡単です。わたしはたとえ注文ミスがあってもすべて買いとりました。いい顔をしようなどというよこしまな気持ちではありません。それが大店の了見だと、祖父に叩き込まれてきたからです」
取引が始まって数年が経ったころ、うれしい申し出がありました。「箱義のためにあたらしい機械を入れたいと思っている。ついては人も雇わなければならない。構わないか」と。戸張さんは二つ返事で応じました。
箱義桐箱店は2007年、福山市に西日本営業所、翌2008年には富山県砺波市へ北陸営業所を開設します。前者は生産拠点、後者は取引先との関係を密にするためです。富山には薬や酒など桐箱を必要とする会社がひしめいています。
桐箱が東南アジアで高評価
「日本の人口が減っていくことは目にみえており、桐箱という文化を次代に残そうと思えば海外市場は外せないと考えていました」
「第2創業」と位置づけるここ10余年の一歩目に足を運んだのは、JETRO(日本貿易振興機構)でした。海外に打って出たいと訴えた戸張さんは、文具をテーマにした展示会への出展を勧められます。
「文具の専業メーカーを集め、海外バイヤーを招待するという展示会です。明らかに場違いでしたが、動かないことには始まりません。見よう見まねながらマウスパッドなどのステーショナリーを製作したところ、審査を通過しました」
そこで出会ったのが、シンガポールのエドウィン・ローさん。空港やアートミュージアムにも支店をもつ指折りのギャラリーショップ「スーパーママ」のCEOです。
ローさんは日本の文化にも造詣が深く、有田焼とシンガポールのデザイナーのコラボレーションで成功を収めていました。その第2弾として、桐箱を目玉に据えます。
ローさんのリクエストで桐箱のほか、燕三条のテーブルウェアやカトラリー、印伝革、だるま、前掛けなど総勢10社が集結。箱義桐箱店は燕三条とのトリプルコラボとなる道具箱などをつくりました。
 シンガポール有数のショップ「スーパーママ」でも扱われています(箱義桐箱店提供)
シンガポール有数のショップ「スーパーママ」でも扱われています(箱義桐箱店提供)
そのコレクションは「Singapore Art Week」やロンドンの「TOP DRWER」といった感度の高い見本市にも並び、世界のバイヤーから注目されました。
足場を固めたもう一国がタイです。戸張さんは2017年、バンコクで行われた国際見本市「フード&ホテル」に出展します。台東区と朝日信用金庫が連携した取り組みで、区内の企業を中心とした15社が参加。箱義桐箱店はまな板や御節の器などを出品しました。
いずれももともと展開していた商材で、お国柄を踏まえ、ゴールドなど華やかな色使いでアップデートしました。
これがきっかけとなり、東南アジアをリードするECプラットフォーム、ラザダとショッピーへの出店を果たします。運営は現地で出会ったパートナーに一任しています。
スマホ専用スピーカーも開発
海外を攻めるかたわら、おひざ元においては若い世代への浸透を図ります。戸張さんは2012年、本社からほど近い東京・谷中へ店を出し、オリジナル商品の開発に乗り出しました。
 芝浦工業大学と開発したスマホ専用スピーカー(6750円)(箱義桐箱店提供)
芝浦工業大学と開発したスマホ専用スピーカー(6750円)(箱義桐箱店提供)
品ぞろえのポイントは、ひとつは主役になれる桐箱、そしてもうひとつは箱屋の目利きで選んだ、桐箱にしまいたい全国の工芸品です。
「桐箱はずっと脇役の存在でした。光を当てるにはどうすればいいか。答えはきっとデザインにあると考えました。といってもわれわれにそのノウハウはありません。よその人の力を借りることにしました」
手を組んだのは芝浦工業大学。シンガポールの取り組みがつないでくれた縁で、2021年、デザイン工学科のプロジェクト演習の一環としてスマートフォン用のスピーカー、眼鏡ケース、スパイスケースの三つを商品化しました。
「じつは桐は音響効果に優れる素材です。古来、琵琶や琴などの和楽器に使われてきました。授業でその話をすると、『現代ならスマートフォンでしょう』となった。まろやかな音を奏でる構造も特筆に値します。われわれには思いもよらない発想であり、技術です。また、眼鏡ケースは軽量性、スパイスケースは調湿効果に目をつけた商品開発であり、すべてが桐の特性を踏まえています」
2024年にはビームスがデザイン監修した「台東屋 ~TAITO-KU STAND~」に参画します。大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」にあやかった台東区の商品開発支援のプロジェクトで、区内の8社が選ばれました。
箱義桐箱店は名所江戸百景をモチーフとした桐箱を作成。入れ子構造となっており、外には往時の地図が、中にはゆかりの浮世絵が描かれています。
 「台東屋 ~TAITO-KU STAND~」にラインアップされた桐箱(単品2970円、セット2万6290円)(箱義桐箱店提供)
「台東屋 ~TAITO-KU STAND~」にラインアップされた桐箱(単品2970円、セット2万6290円)(箱義桐箱店提供)
確実に裾野を広げることができたと充実感をにじませる戸張さんは、ゆくゆくはデザインも内製したいと意気盛んです。
直営店にはまた別の思いもありました。
「広島の家具メーカーも廃業が続いています。わたしは、生計を立てる手立てを失った職人や作家が活躍できる場をつくりたかった。店に置くだけでなく、ポップアップストアもたびたび開催してきました。おかげさまで半年先までスケジュールが埋まるイベントに成長しました」
あくまで応援したいという気持ちの表れであり、ポップアップストアの出展料はとっていません。「いただくのはマージンのみで、ひとつも売れなければ費用は1円も発生しません」
承継にも思いを巡らせて
「第2創業」の前後で比較すれば、売り上げは倍増しました。見事に花を咲かせた戸張さんですが、その口ぶりは種をまいたに過ぎないといわんばかりです。
「ブランドイメージの向上に寄与したのは確かですが、海外の売り上げは1割程度ですし、直営店もまだまだこれからですから」
還暦を目前に控えた戸張さんは、一線を退いた後のことにも思いを巡らしています。
箱義桐箱店には戸張さんの弟が2人おり、まずは兄弟に譲るとして、その先をどうするのか。「桐箱に文化的価値を感じていただける方なら親族外承継もやぶさかではない」といいますが、本音は別のところにありそうです。
「なにをやるにせよ、これからは海外だと口を酸っぱくしていってきた長女が商社に採用されました」
長女の真意はわかりませんが、商社で経験を積めば戸張さんの右腕になる未来もみえてきます。
「承継を見据えたものかも知れませんね」と水を向けると、「わたしからはひと言も継げといった覚えはないんですけれどね」といって、目を細めました。