子どもの玩具離れでも市場は堅調 経産省が示す産業発展への3つの方向性
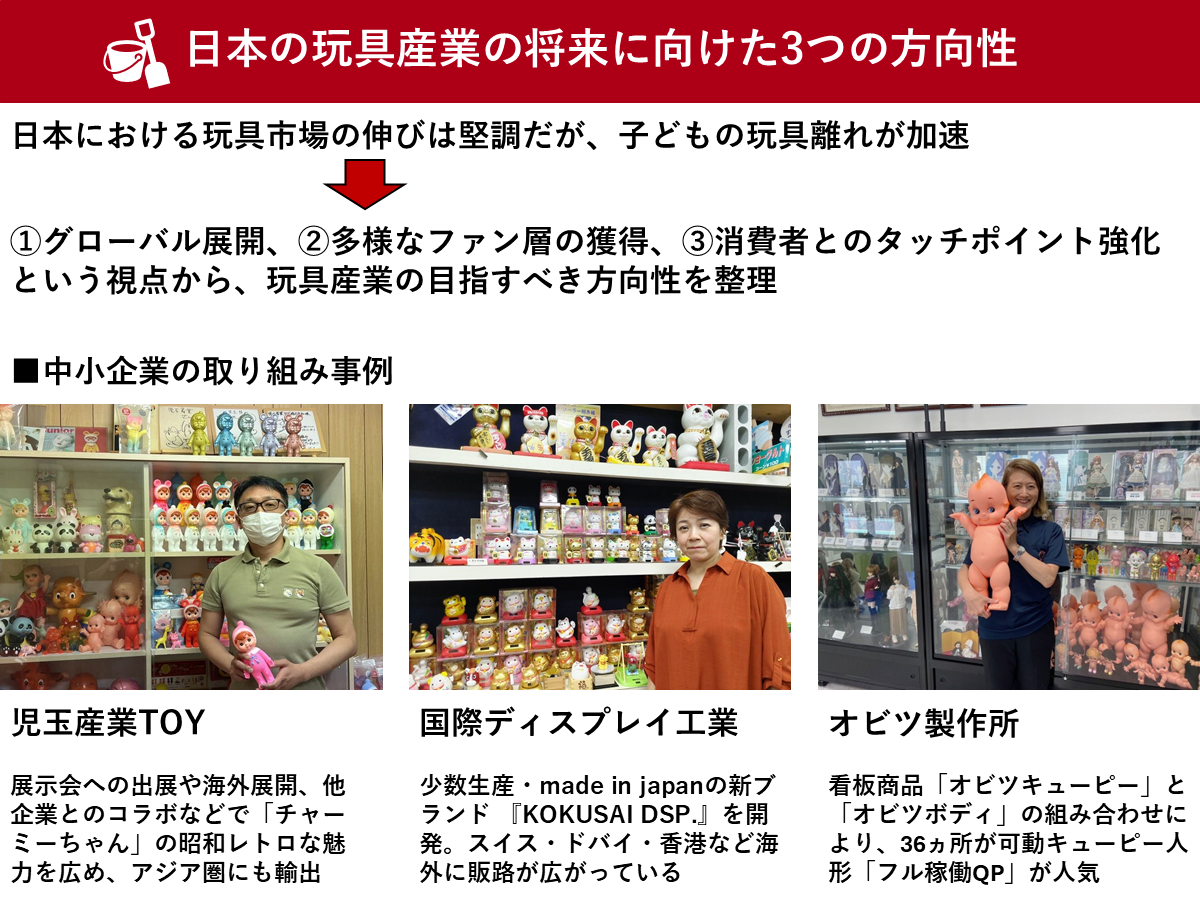
子どもの玩具利用機会の低下や玩具離れ、海外市場の成長取り組みなど、我が国玩具産業は複数の課題を抱えているなか、経済産業省が立ち上げた「玩具の価値を考える会」は中間とりまとめのなかで、①グローバル展開、②多様なファン層の獲得、③消費者とのタッチポイント強化という3つの指針を示しました。
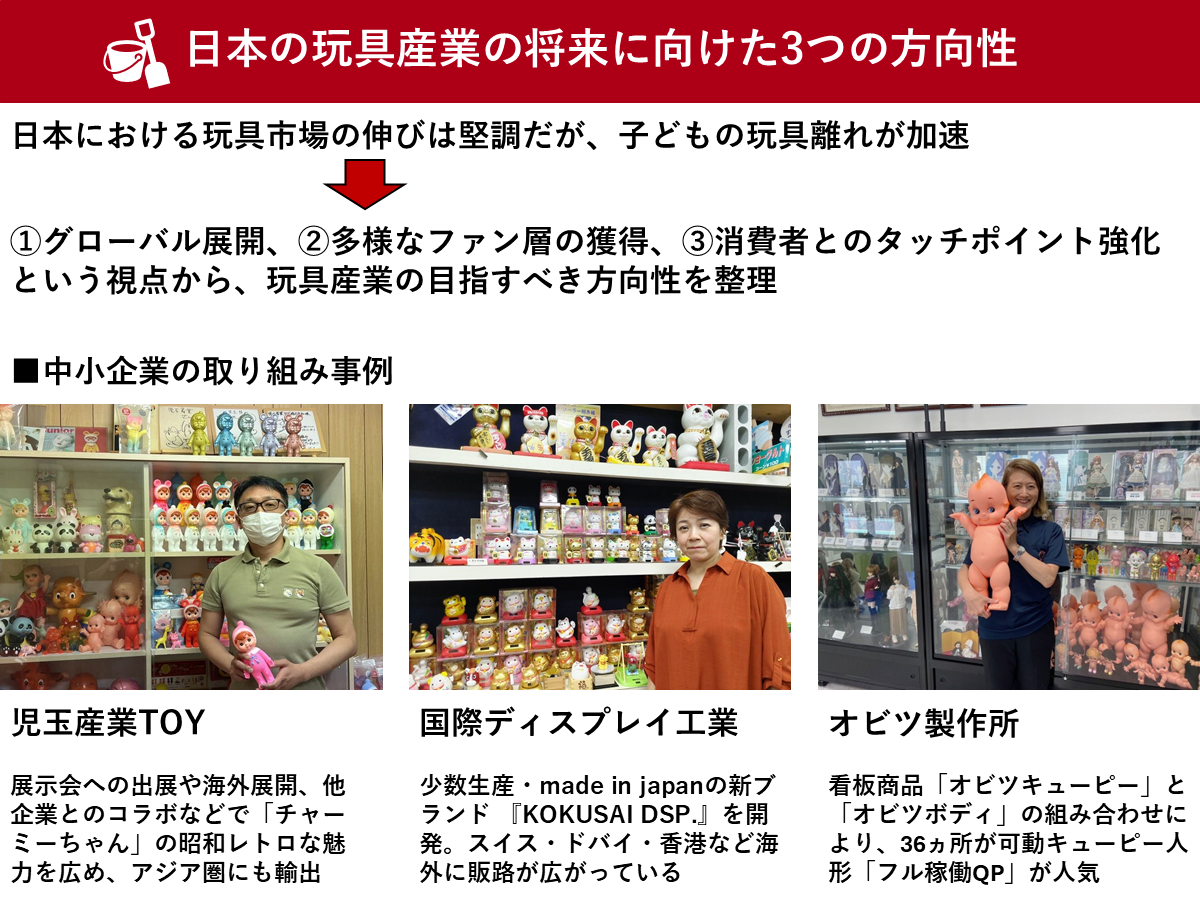
子どもの玩具利用機会の低下や玩具離れ、海外市場の成長取り組みなど、我が国玩具産業は複数の課題を抱えているなか、経済産業省が立ち上げた「玩具の価値を考える会」は中間とりまとめのなかで、①グローバル展開、②多様なファン層の獲得、③消費者とのタッチポイント強化という3つの指針を示しました。
目次
近年、子どもたちの遊びの風景は大きく変化しています。0歳から9歳までのインターネット利用率は74.4%に達し、そのうち約3割がスマートフォンやタブレット端末を利用しているというデータもあるなか、従来の「アナログ型玩具」との接点が減少する「子どもの玩具離れ」が懸念されています。

しかし、日本国内の玩具市場は、15歳未満人口が減少を続ける中でも堅調な伸びを見せ、2023年度には過去最高となる1兆193億円を記録しています。これは、節約とぜいたくの「メリハリ消費」や、大人向け玩具の需要増大を示す「キダルト消費」といった新たなトレンドが市場を牽引しているためと考えられます。
日本の玩具産業が持続的な発展を遂げ、将来にわたって競争優位性を維持し、世界市場を獲得していくためには、環境変化への対応が不可欠です。
経産省は、有識者を集めた官民共同の検討会「玩具の価値を考える会」を設置しました。海外展開、知育玩具の普及拡大、玩具産業の現状と課題、消費者とのタッチポイント強化といった論点を議論し、その中間取りまとめとして、玩具産業振興の新たな指針を作りました。
具体的には「グローバル展開」「多様なファン層の獲得」「消費者とのタッチポイント強化」という三つの方向性を打ち出しています。
以下に、それぞれの方向性について詳しく解説します。
まず、グローバル展開の現状・課題を整理すると、多くの日本の玩具メーカーは、海外展開に関する知識不足や過去の成功体験からの脱却が不十分なため、海外市場への進出にためらいがあります。日本のコンテンツ(IP)と連携したグローバル展開は、IPホルダーとの権利関係の複雑さや各国のコンテンツ嗜好の違いを把握する難しさから、まだ十分ではありません。
企業が輸出を行う際の主な課題として、「現地における販売・流通網の発掘・拡充」や「市場動向や関連規制などに関する情報収集」があります。また、模倣品対策として国ごとに知的財産権の取得が必要ですが、コスト負担が大きいという課題があります。
こうした課題の解決策の一つとして、世界で競争優位性を持つ日本のコンテンツとの連携を推進することを挙げています。海外展開の際、小規模で乏しい経営資源を有効に使い、大企業がカバーしないニッチ市場において競争優位を高めるためには、「コンテンツとの連携」、「流通網の確立」が重要となっています。
成功事例として、日本発の金属製鋳造パズルシリーズである「はずる(Huzzle)」があります。1983年に発売されて以来、現在では57の国と地域で発売され、累計販売数は2600万個以上に達しています。
また、未開拓国に進出する際は、既にその国で事業を展開している玩具メーカーの協力を得て、その会社の流通網を活用するのがよいでしょう。2023年に発売された「ゼルダの伝説」とのコラボ商品は、世界で累計42万個を販売する大ヒットにつながっています。
OTTサービスなどの普及により日本のアニメコンテンツが世界中で認知されており、ホビー玩具などをタイムリーに販売することがますます重要になっています。
このほか、北米市場における知育・教育玩具の高い成長率を踏まえ、日本のSTEAM教育玩具や言語取得に役立つ玩具と、北米で人気の日本発コンテンツとの連携を進めることも一つの手段でしょう
少子高齢化やデジタルシフトが進む中で、多様化する消費者ニーズに対応し、幅広い層に玩具の価値を届けるための方向性も大切です。
消費者の価値観が多様化し、個人の嗜好だけでなく、社会的責任や環境への配慮も重視されるようになっています。
従来の「玩具は子どもが家で遊ぶもの」という認識は過去のものとなり、玩具は全年齢・世代を対象とした商品化が進んでいます。
日本の多くの企業が従来のターゲット層に固執しており、STEAM教育などの高度な知育ニーズやデジタルを活用した玩具ニーズへの対応が遅れていると指摘しています。
そこで、指針ではまず、玩具の「機能的価値」を再評価し、魅力ある玩具を開発することを勧めています。玩具は幼児の心身の発達を促進し、学習をサポートするだけでなく、高齢者の心身の健康づくりにも活用され始めています。
その機能について科学的エビデンスを取得・付加することで、知育・教育玩具の「世界共通の基準(共通のモノサシ)」を確立する必要性があります。これにより、製品・サービスの質が向上し、購入者のリテラシーも高まることが期待されます。
玩具の「情緒的価値」も追求し、魅力ある玩具を開発し、日本のコンテンツと組み合わせることも重要です。
多様化する消費者の遊びと購買行動に対応し、玩具と消費者の接点を強化するための方向性も大切です。

スマートフォンやテレビゲームなどのデジタルコンテンツの普及により、子どもたちの玩具の利用機会が減少しているほか、玩具のタッチポイントが玩具専門店からECなど多様なチャネルに移行し、従来の販売方法では玩具の魅力が伝わりにくくなっています。
玩具メーカーや小売店からは、カードゲームに市場シェアが偏り、純玩具のヒット商品が不足しているとの声もあります。とくに中小企業は費用対効果の面で消費者との接点を増やすことに苦戦しています。
そこで、子どもとの直接的な接点を増やすことが重要だと指摘しています。アソボーフェスタのようなイベントを活用すること、購入後にどのような楽しい体験が待っているかを消費者に訴求できるといいます。
デジタルチャネルの活用として、UGC(ユーザー生成コンテンツ)のECサイトでの表示なども紹介しています。ただし、バーチャル空間における過度な依存や個人情報漏洩といった潜在的リスクを認識し、安心・安全に玩具を楽しめる環境を提供することが求められます。
従来のファン層だけでなく、市場を広げようとしている事例を紹介します。
東京都葛飾区の児玉産業TOYは、ソフトビニール人形「チャーミーちゃん」の製造販売で知られています。前身企業から数えて4代目の児玉洋祐さん(45)は、経営危機に直面しながらも、展示会への出展や海外展開、他企業とのコラボなどで「チャーミーちゃん」の昭和レトロな魅力を広めました。
現在はアジア圏を中心に、生産が追いつかないほど輸出量が増えています。
東京都葛飾区のオビツ製作所は、ソフトビニール製の人形などを製作する会社です。プラスチック成形方法の一つである「スラッシュ成型」でつくられる「オビツキューピー」や「オビツボディ」などの商品は、高い品質と愛らしさで国内外のファンの熱い支持を得ています。
従業員にやりたいことを募るようにしたところ、新商品が次々に誕生しました。
そのひとつが、「フル可動QP」。看板商品の「オビツキューピー」と「オビツボディ」の組み合わせにより、36ヵ所が可動のキューピー人形が2014年にできあがりました。究極の社内コラボと言えるフル可動QPは、前代未聞の外観が面白がられ、ロングセラー商品になりました。
国際ディスプレイ工業(東京都文京区)は製品の企画・開発・製造・販売を手掛けている、ソーラートイとムービングディスプレイのパイオニア。
2012年、少数生産・made in japanの新ブランド 『KOKUSAI DSP.』 をリリースしました。その後、シリーズ化に成功し、展示会に出展すると、瞬く間に海外のバイヤーたちの目に留まり「これを仕入れたい」「とても素敵だ」という声がダイレクトに入ってくるようになりました。
積極的に売り込まなくても、スイス・ドバイ・香港と驚きのスピードで海外に販路が広がっていったのです。日本国内でも広がりはあり、蔦屋書店やロフト、東急ハンズなどで展示・販売されています。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。