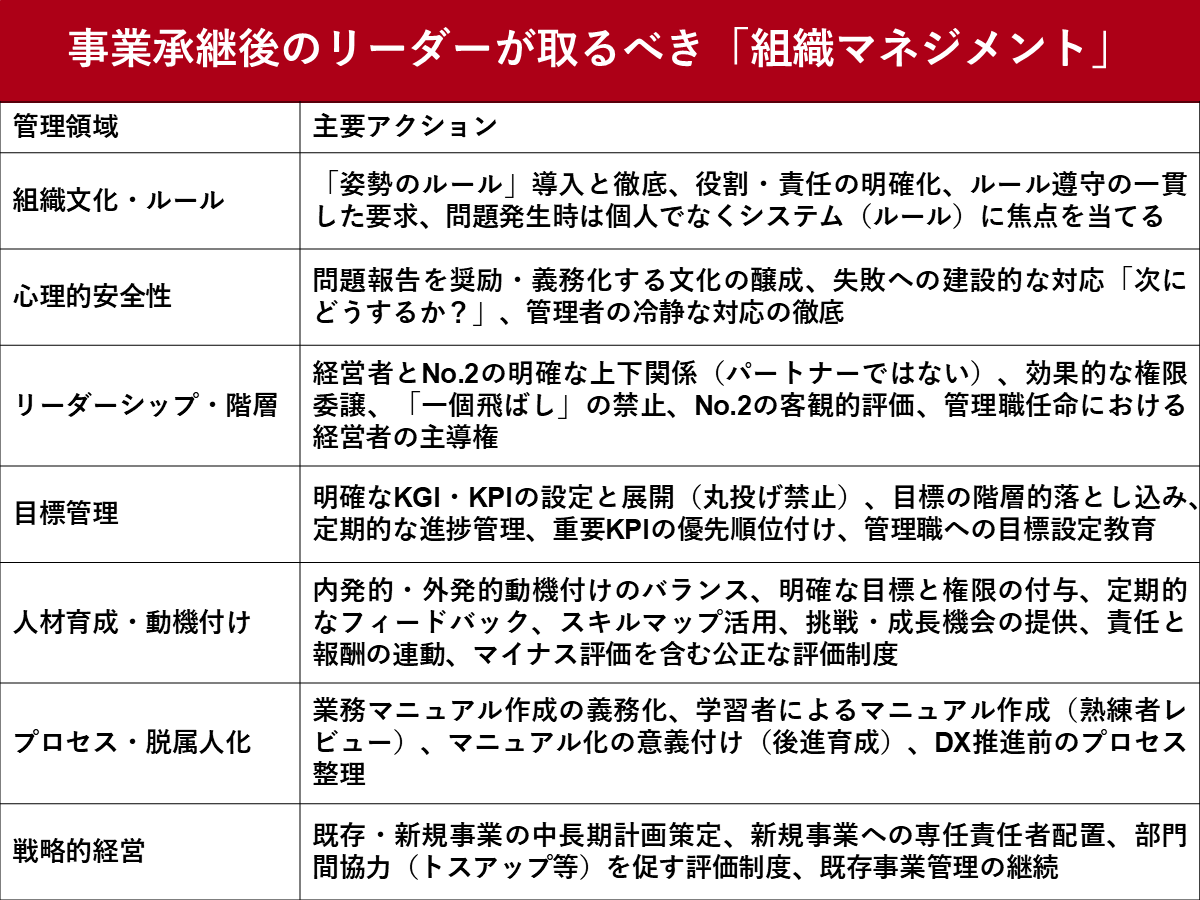製造業は基本的に、ある規則的な業務を繰り返していく仕事と言えます。それゆえ、生産性の向上を図るには個別に業務の見直しをすべきだと考えられがちですが、それよりも先にやることがあります。それはルールの整備です。
こう述べると、「当社はしっかりとルールを定めているから問題ない」と考える経営者がいますが、本当でしょうか。全従業員がルールを念頭に置いた上で作業にあたっているでしょうか。
筆者が中小企業の製造現場を訪れ、経営者に聞いたルールを従業員に確認すると、「初めて知った」、「マニュアルを最初に一度読んだだけ」という反応が返ってくるケースは珍しくありません。ルールがあっても形骸化している現場では、従業員がその都度、独自の判断を強いられます。それが迷いを生み、生産性の低下につながるのです。
従業員が普段からルールに基づいた行動をしていないと、経営者が新しい方針を打ち出した際、「何が何でもその通りに動こう」とする意識が従業員の間に生まれません。「ああ言っていたけれど、面倒だし今まで通りでいいよな」と従業員が勝手に判断してしまうのです。
そんな状況を改善するにも、奇抜なルールは不要です。整理整頓の仕方やトラブル発生時の報告フローなど、仕事をする上で意味を持つルールを明文化します。工場や物流倉庫のルールは会社間で大きな違いはありません。知人の会社やメディアで見た会社のルールをまねしてみるのはいかがでしょうか。有名なトヨタ自動車の「かんばん方式」でもいいでしょう。最初からオリジナル性を出そうとせず、まずはまねをして、運用する過程でブラッシュアップしていけば十分です。
ルールを決めたら、それを順守させる役割と責任を管理職に与え、従業員全員が徹底して守る体制を整えましょう。その際に、経営者からよく挙がるのが「最初はルールを守っていたのに、注意されないから誰も守らなくなった」という声です。この原因はどこにあるのでしょうか。
それは、指導する責任が誰にあるかが決まっていないために、よく起きる現象です。
製造業に限らず、中小企業は主任、係長、課長、次長、部長などの役職者を大勢抱えている傾向があります。名ばかりの管理職があふれていると、責任の所在がややこしくなりがちです。
筆者の経験上、中小企業の役職者は実際の半分で足ります。
ある工場では、ルールの明文化と徹底、注意する責任を明確にしただけで、1カ月間、作業者起因による不良がゼロになりました。これは、創業30年以上の歴史で初めてとのこと。これだけで生産性は十分向上するのです。
元工場長のルール違反が大事故に
ルール違反をしてばかりなのに生産性の高い従業員はいますが、それは例外です。たまたま本人の適性や好みが現在の業務に合っていて、自然と成果が出ているに過ぎません。それを受けて、経営者が「あなたは仕事ができるからルールを守らなくてもよい」と宣言してはマネジメントが機能しなくなります。
あるいは、自分より年上の従業員には指示しづらいと悩む管理職もいるでしょう。しかし、そういう社員の放置こそ要注意。生産性が高いように見えて実はトラブルメーカーかもしれないからです。
リサイクル業を営む会社で実際にあった話をご紹介します。
その会社の工場長は定年で職を辞した後、再雇用制度の下、一般の作業員として現場に復帰しました。元工場長であるため、上司になった従業員は彼にしてみれば経験の浅い若手です。
元工場長は上司の指示を受けるといったんは素直に聞く振りをするのですが、あくまで振りだけ。例えば、上司が資材の保管場所を何度指定しても、毎回違う場所に置こうとします。「ここに置いた方がやりやすいからさ」と返す元工場長に、上司側も強く言えません。
そんな状況が続いたある日、大事件が起こりました。元工場長がコンベヤーに入った異物を取ろうとした際、腕を挟まれて骨折したのです。
コンベヤー内に異物が入ったときは、それを取り除くために一時的に稼働を停止させなければなりません。もちろん、その会社でもそのようにルールが定められていました。
ただ、一度停止させてしまうと再稼働のために10~15分待たなければならず、生産性が低下します。従業員にとってはそのロスをいかに少なくするかが腕の見せどころですが、だからといってコンベヤーを止めずに異物を取り除くなど言語道断です。
元工場長であってもしっかりルールを守らせる必要がありました。ヒトは良かれと思って最善を選びます。注意されなければ「これは守らなくてもいいのだ。」と勘違いしてしまうのです。元々ルールを作って守らせる立場にいた人ですら、立場が変わればそうなってしまいます。
公明正大な評価制度の整備を
「私は成長を求めていない。ルーチンワークがいいから今の仕事を選んだ」という社員がいたとしましょう。製造業ではあり得る話です。
こういう社員は短期的な視点を持ってしまっています。社会人は成長を続けなければ周りに置いていかれ、評価を獲得できません。万が一、その会社が倒産したら何のスキルもない状態で社会に放り出されてしまいます。どんな場所であっても活躍できるようにしてあげることが本当の優しさのはずです。
ただし、従業員が変化を好まないのは、変化した先に何があるかが見えないせいとも捉えられます。それこそ、作業スピードが倍に増えても給料が変わらないならだらだら仕事をした方が得でしょう。それに、社歴も長く、年齢もはるか上の先輩がイキイキと働いていなかったら、この会社で出世したいとは思いません。
経営者にとって大切なのは、明確な評価制度の整備です。何ができるようになれば立場が上がり、どのくらい給料が増えるか、公明正大な仕組みを作る必要があります。
その際、「リーダーシップを発揮する」、「会社に貢献する」といったあいまいな指標ではなく、「作業の全工程を3時間以内にミスなく一人で担当できる」といったように、誰の目から見ても基準がぶれない形にしてください。
身売りを選んだ経営者の共通点
製造業では規則的な業務に取り組む機会が多いため、経営者がこれまでのやり方を大きく変える施策を提案をすると、「逆に生産性が落ちます」と現場から反発が出てきます。
それでも、慣れた後を考えれば変更に踏み切った方がよい場合は多々ありますし、何事もやってみなければ分かりません。同じやり方を続けている限り生産性は向上せず、技術が陳腐化して他社に追い越されるリスクが付きまといます。
以前、従業員数20~30人の製造業の経営者10人と立て続けに面談をしました。その経営者たちは全員がM&Aによって会社を売却した元オーナー社長。要するに、経営に行き詰まって事業再生を依頼したのです。
その10社には共通点がありました。それは、会社が立ち行かなくなるくらい業績が悪いのに過去10年間社員が辞めておらず、そして誰一人として昇給・昇格していないことです。
いずれの経営者も既存事業がうまくいかず、必死で新事業に乗り出そうとしていましたが、全て自分一人で抱えていました。他の従業員に任せれば離職されてしまうと思い込んでいたのです。
従業員にしてみれば、給料が変わらないとはいえ、慣れた作業をさせてくれる今の会社にいた方が転職先を探すよりもいいのでしょう。多少会社に文句があっても辞めはしません。
しかし、経営者が従業員に成長を求めなくても、従業員自身は市場から成長を求められます。10人の経営者はみんな私財を投じ、時には借金をしてまで従業員に給料を支払っていました。その結果が身売りです。これでは会社を経営する意味がありません。
会社を発展させようとするなら人は入れ替わります。現状維持は利益ではなく衰退です。経営者は必要とあらば覚悟を持って改革に乗り出すべきでしょう。
技能継承する側にインセンティブ
製造業のなかでも、極めて高度な技術を必要とする仕事であるほど、その伝承が簡単ではなく、特定の従業員にしかできない工程が生まれてしまいがちです。そうすると、その従業員が体調不良になったり、けがで長期間の離脱を余儀なくされたりしたら生産性の低下に直結します。
それを防ぐためにも仕事のルール化、つまりマニュアルの作成によって職人の技術を共有し、後進を育成すべきでしょう。最近のテクノロジーを使えば、動画を撮影し、それを基にして簡単にマニュアルを作成できます。
とはいえ、経験豊かな職人が直接指導しなければ伝わらない感覚は間違いなくあります。職人から職人へそれを伝えていくには、伝える側にメリットがある仕組みを築かなければなりません。
とにかく作業を黙々とこなしたい職人がいたとしましょう。その職人に経営者が「空いている時間に技術指導もしてください」と言うだけだったら、「なぜそんなことしなくちゃならないんだ……」と不満を抱かれるでしょう。
優秀な職人に作業と指導の両方を平行して求めると「教えるのは面倒だから自分でやる」という状況になりがちです。
そうならないよう、例えば「あなたの役割は後進の育成です。部下5人全員が半年以内に◯◯のレベルに達するように育成してください。それによってこういう評価が得られます」と言い切るのです。もちろん、職人として活躍してもらうのは問題ありませんが、他のメンバーを指導する時間を優先して確保させるのです。
育成の役割を明確にし、その役割を全うすれば大きな利益があると分かれば、上に立つ従業員はその役割を果たそうとするでしょう。この仕組みが回り出せば、組織が飛躍的に成長します。
以上、製造業で生産性向上を図るためのポイントを解説しました。本記事が、少しでも参考になれば幸いです。
羽石晋さん
識学上席コンサルタント コンサルティング部 課長
埼玉大学教育学部を卒業後、人材サービス企業のランスタッド株式会社に入社。支店長職を経て、関西中部エリア、中四国エリアのエリアマネージャー、再就職支援部部長を歴任し、識学に入社。
(※構成・平沢元嗣)