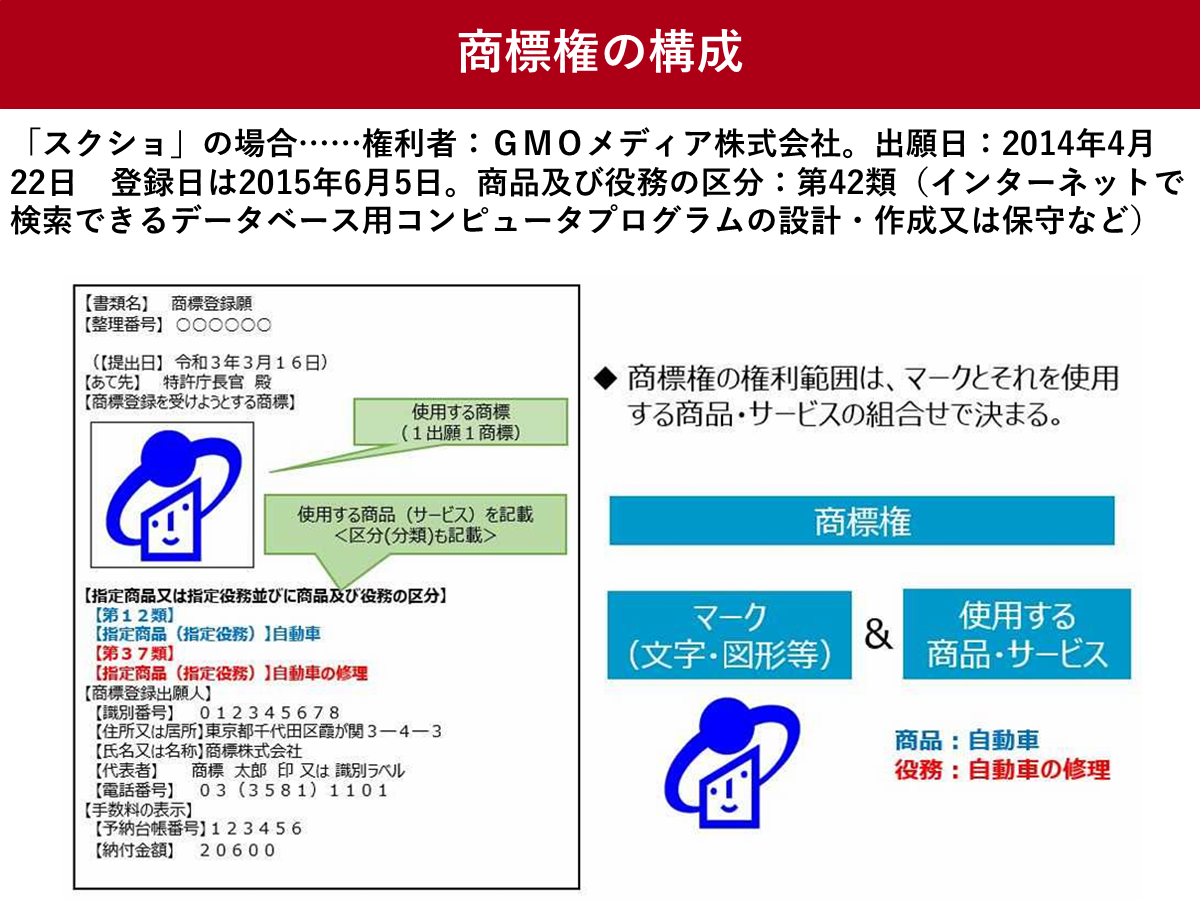こうした結果、2024年8月時点で、全国の約27.9%の市区町村には書店が存在しない状況となっています。背景には、単なる「本離れ」だけではない、構造的な課題が存在します。経済産業省の報告書案が指摘している課題のなかから3つを紹介します。
書店の粗利率は約22%程度と低く、「委託配本制度」の下で書籍が33.4%、雑誌は47.3%返品されており、この返品コストも書店経営を圧迫する一因となっています。
再販売価格維持制度により、人件費や物流費、キャッシュレス決済手数料などのコストが上昇しています。しかし、再販売価格維持制度により、出版社が決めた価格で、全国一律の価格で販売されているため、店舗運営のコスト上昇などを販売価格に転嫁できない状況となっています。
時代のトレンドを映す書店 一覧性と編集力に強み
厳しい経営環境にあるとはいえ、リアルな書店空間には、オンラインでは得難い情報収集のメリットがあります。その一つが、書店の持つ「一覧性」です。
書店員が工夫を重ねて、棚に様々なジャンルの本がたくさん並んでおり、一気に視野に入る点が非常に重要であると経産省の資料でも指摘しています。
もう一つが、編集力です。一覧性とも重なるところがありますが、雑誌や書籍コーナーを見渡すと、本の並び、陳列方法により、一冊ずつの本では表現できない世の中のトレンドを知ることができます。また、目的の本を探しているなかで、ふと目にした本から潜在的なニーズに気づけたりすることがあります。
新しい発想に必要なひらめきと観察力を磨ける書店
書店の一覧性や編集力を新規事業開発に生かそうとしているのが、中小企業支援から、大企業の新規事業開発までを支援している秋元祥治さんです。
 秋元祥治氏 - 事業創出家 / 株式会社やろまい代表取締役 / 岡崎ビジネスサポートセンター チーフコーディネーター / 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部・EMC教授 / NPO法人G-net 理事等
秋元祥治氏 - 事業創出家 / 株式会社やろまい代表取締役 / 岡崎ビジネスサポートセンター チーフコーディネーター / 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部・EMC教授 / NPO法人G-net 理事等
新しい発想に必要な要素の一つが、「圧倒的で雑多な情報量」のインプットだといいます。書店は、自分の興味関心とはかけ離れた情報も含め、膨大かつ多様な情報があふれています。
普段目にしないジャンルの本棚まで観察することで、市場のトレンドやマーケットの温度感をつかむことに役立つとして、たまに書店に足を運び30分ほど観察してみることを勧めています。
女性誌を見比べるだけで、年齢や生活スタイルによって細かく分類されたニーズがあることに気づきます。ほかにも、SNSでも時折話題となる1974年創刊住職の実務誌「月刊住職」を買ってみると、お寺の「セルフ葬」や「読経に誤嚥性肺炎の予防効果あり」など新たな切り口を提供してくれます。
インプットした情報は「タグ付け思考」で整理をします。 書店で見つけた気になる書籍、雑誌の特集について、関連するキーワードを頭の中でハッシュタグのように付けていく思考法です。
頭のなかで整理しておくことで、別の情報に触れたり、顧客のニーズ・課題に出会ったりしたときに結びつけやすくなるのだといいます。
たとえば、秋元さんが「ホット専用水出しコーヒー」という商品をヒット商品に生まれ変わらせたときは、「忙しい朝でも、本格的で美味しいコーヒーが簡単につくれる」という強みから連想ゲームのように「#本格コーヒー #手軽 #手間なし #誰でもできる #忙しい朝 #時短……」と展開していきました。
その結果、「忙しい朝でも、手軽に本格コーヒーが飲める」という切り口を見つけ、「年間50時間節約できる水出しコーヒーGet!50」として生まれ変わりました。
 年間50時間節約できる水出しコーヒーGet!50
年間50時間節約できる水出しコーヒーGet!50
秋元さんは、こうした発想を生み出すために日々インプットを重ねているそうです。
「タグ付け思考」は、書店で得られる雑多な情報を、単なる知識の断片ではなく、いつでも引き出して組み合わせられる「アイデアの素材」へと転換させるための、実践的な認知ツールと言えます。
新規事業アイデアを探しに有隣堂へ
実際に有隣堂アトレ恵比寿店を訪れてみました。正面入り口には、「Even if not many」というテーマで、左利き用のグッズや誰にとっても着やすい服などともに「アート×福祉」プロジェクトの本や「利他」をテーマにした書籍が並んでいました。
 有隣堂 アトレ恵比寿店の特集コーナー(店舗の公式Instagramから https://www.instagram.com/yurindo_ebisu/)
有隣堂 アトレ恵比寿店の特集コーナー(店舗の公式Instagramから https://www.instagram.com/yurindo_ebisu/)
隣のコーナーでは、イギリス発のレジャーブランドのバッグと一緒に旅に持ち運びやすい文庫本、イギリスをテーマにした本があり、雑誌コーナーでも「睡眠」をテーマにして、Newtonの「睡眠のサイエンス」などとともに「疲労回復ウェア」をうたう衣類が本棚で売られていました。
書籍担当の大平雅代さんは、特設コーナーのテーマとなるトレンドの見つけ方、作り方について「同僚たちの好きなテーマから発展させたり、普段の展示会やショーなどを見て回ったり、雑誌でよく取り上げられているテーマから気づきを得たりといろんなところからヒントを得ています」と話します。
偶然の出会いをもたらす探索活動
情報収集ツールは本や雑誌に代わり、インターネット検索が伸びてきました。本を探すときもネット書店を使う人が増えています。
しかし、その効率性と引き換えに、オンラインでの情報収集には限界があります。たとえば、自分の興味関心のあるテーマの探索から始まるため、既に知っていることの周辺情報が集まります。
リアルな書店が提供する最大の価値の一つが「セレンディピティ(偶然の出会い)」です。ネットでは見つけられなかった本と出会い、本来なら結びつかないような情報がむすびつき、新たなアイデアへとつながる可能性があります。
書店への訪問は、コスパのよい知の探索活動とも言えます。既存のリソースである「街の書店」へ、これまでとは違う「観察をする」意識で足を運んでみませんか。ビジネスを飛躍させるチャンスが書店の片隅で待っているかもしれません。
ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。