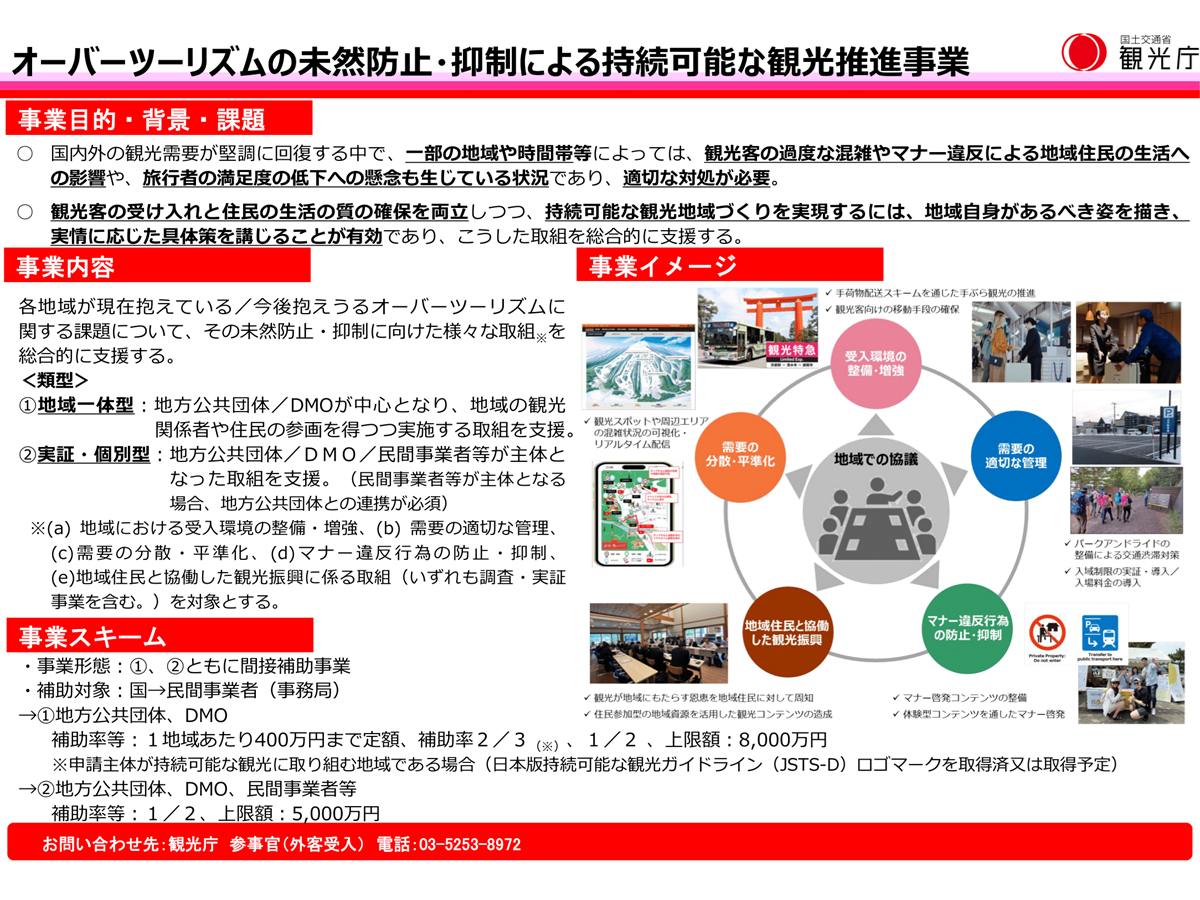少人数会合が、現地時間7日午前11時55分(日本時間8日午前1時55分)から約30分間あり、拡大会合(ワーキング・ランチ)は現地時間8日午後0時25分(日本時間8日午前2時25分)から約20分間ありました。
その後の共同記者会見で、トランプ氏は日本製鉄がUSスチールを買収することについて「USスチールは我々にとって非常に重要な企業だ。この地を去るわけではないが、構想は心理的に良くない。だから彼らはUSスチールを所有するのではなく、多額の投資をすることに同意した」と発言しました。
1901年設立。長い歴史を持つ企業で、鉄鋼製品の製造と販売を行い、建設や自動車、エネルギーや家電など多岐にわたる産業向けに鋼材を供給してきました。
第二次世界大戦中、USスチールは軍需産業の一環として重要な役割を果たし、大量の鉄鋼を供給し、収益が急増しました。
しかし、1970年代以降、日本や韓国などのアジア諸国の製鉄業が急成長し、低コストで高品質な鉄鋼を供給し始めたことにより、USスチールの市場シェアが減少しました。また、USスチールは経営の失敗や戦略の誤りにより、経済的な問題に直面して多くの資産が売却され、企業の規模が縮小していき今日に至っています。
日本製鉄の資料によると、日本製鉄は、USスチールに対し、2023年12月に米国子会社であるNIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.を通じ、米国の高炉・電炉一貫の鉄鋼メーカーであるUSスチールを買収することと、USスチールとの間で本買収に関する合併契約を締結することを決定したと発表しました。
しかし、2025年1月、バイデン前大統領が日本製鉄によるUSスチール買収を阻止する姿勢を正式に発表しました。
バイデン前大統領は以前から買収に対して懸念を示していましたが、USスチールのような米国を象徴する企業が外国企業の支配下に置かれることは、米国の国家安全保障を脅かす恐れがあるとしており、それを阻止することは米国大統領としての責務であるとしました。
外国企業による対米投資に伴う安全保障上のリスクを審査する対米外国投資委員会は、最終判断をバイデン前大統領に一任していたことから、買収は難しくなりました。
これに対し、日本製鉄とUSスチールは1月6日、買収に対する不当介入の是正を求めるとして、2件の訴訟を共同で提起したことを公表(日本製鉄のニュースリリース)。以下のようにコメントを発表しました。
本買収は、米国鉄鋼業がある地域の再活性化、米国の鉄鋼サプライチェーンの強靭化、中国鉄鋼業の脅威への対抗に向けた米国鉄鋼業の強化をもたらします。日本製鉄は、USスチールの従業員、同社が事業を行う地域コミュニティ、及び米国鉄鋼業界全体の利益のために、USスチールを支え、成長させるために必要な投資を行うことができる唯一のパートナーです。既にコミットしている27億ドルの投資の一環として、ペンシルバニア州モンバレー製鉄所に少なくとも10億ドル、インディアナ州ゲイリー製鉄所に約3億ドルの投資を行うことを決定しています
さらに、2月3日には原告準備書面を共同で提出しました。訴訟に関する資料は日本製鉄とUSスチールの共同サイトにアップロードされています。
日本側だけでなく、USスチールからも反対の意見が示され、日本製鉄は徹底抗戦の構えを崩していません。
バイデン前大統領が買収を阻止した2つの背景
バイデン前大統領が買収阻止に徹した背景としては、2つの要因が考えられます。
まず、2024年秋の大統領選挙で民主党は敗北しましたが、獲得票数ではトランプ大統領の圧勝というわけではなく、まずは2026年秋の中間選挙を見据え、バイデン前大統領には民主党の政治的立場を可能な限り有利にしたいという狙いがあったと考えられます。
仮に、買収賛成に転じれば、バイデン政権の評価は地に落ちるだけでなく、トランプ大統領が民主党批判を展開することは疑いの余地がなく、民主党の政治的立場がいっそう厳しくなる恐れがあります。
また、対中警戒感もあったでしょう。対米外国投資委員会は日本製鉄の中国との関係を慎重に見極め、2024年4月には民主党の上院議員がその関係を危惧する書簡をバイデン前大統領に送っています。
日本製鉄は7月、中国の宝山鉄鋼との合弁を解消し、その事業から撤退することを発表しましたが、バイデン前大統領は日本製鉄と中国との関係が依然として完全には払拭できないと判断したことが考えられます。
買収阻止、経済安全保障協力政策との矛盾も
しかし、背景がどうであれ、買収阻止は4年間のバイデン政権による経済安全保障政策に逆行する動きです。
バイデン前大統領は、中国による経済的威圧や過剰生産、不当廉売などに強い懸念を抱き、それに対処する上で同盟国や友好国とサプライチェーンの強靱化、フレンドショアリングなどを重視してきました。
また、2022年10月、中国が先端半導体を軍事転用するリスクを回避するため、先端半導体そのものの獲得、その製造に必要な材料や情報、技術の流出防止を目的とする輸出規制措置を導入しましたが、米国のみでは完全に防止できないとの判断から、先端半導体の製造装置で高い技術力を誇る日本とオランダに足並みを揃えるよう要請しました。
この際、バイデン前大統領は安全保障上の理由を提示し、対中輸出規制を開始した両国に強化を求め、韓国やドイツなどにも参加を呼び掛けましたが、これはバイデン政権が進めてきた経済安全保障協力の一環です。
一方で、世界の鉄鋼市場で中国が6割以上のシェアを持ち、競争力がないUSスチールの再生を目指すべく、競争力を持つ日本製鉄が買収することは両社にとってウィンウィンなものであるだけでなく、日米という国家間の経済安全保障協力を強化できるという点でも大きなメリットがありました。
何より同盟国との経済安全保障協力を重視するバイデン政権の方針に合うものであったはずです。それにもかかわらず、今回の買収阻止はバイデン政権が4年間積み上げてきた経済安全保障協力に釘を刺すようなものであり、矛盾と非一貫性を露呈し、同盟国との間に一つの亀裂を生んだことは間違いないでしょう。
注目されるトランプ大統領の対応
では、トランプ大統領はこの問題にどう対応していくのでしょうか。
日本製鉄の森高弘副会長は2月6日の決算会見で様々な働きかけをしていることを明らかにし「トランプ政権が進める製造業復権に合致している」と発言。さらにトランプ米大統領がホワイトハウスで米鉄鋼大手USスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者(CEO)と面会したと複数の米メディアが報じています。
トランプ大統領は米国を再び偉大な国家にするため(MAGA)、諸外国から最大限の譲歩や利益を引き出し、諸外国が持つ負担の米国への影響を最大限抑え、米国の政治的安定と経済的繁栄を追求します。そして、米国が世界で最も強い国であることにもプライドがあり、その政治経済的優位を脅かそうとする中国に厳しい姿勢で臨んでいます。
トランプ大統領は以前、「日本製鉄による買収には断固として反対する、買収者は注意するべきだ」と投稿したことがあり、トランプ大統領にとって、USスチールのような米国を象徴するような企業が外国企業に買収されることは、一種の経済的侵略に映っていたのかも知れません。
そこで、今回、トランプ大統領は、日本製鉄がUSスチールを所有するのではなく、「多額の投資をする」という見方を示しました。
対米投資、悲観的にとらえる必要はない
では、今後の日米間の経済関係はどうなっていくのでしょうか。日本製鉄による買収阻止により、今後日本企業による米国企業の買収の動き、米国への投資の動きが後退する懸念も聞かれていましたが、これについてはそれほど悲観的に捉える必要はないでしょう。
無論、日本企業がトランプ関税の影響を受けることは間違いありませんが、日本は2019年以降、世界最大の対米投資国であり、何より日本企業が米国へ投資し、米国内の経済を活性化させようとすることは、トランプ大統領が目指すMAGAにフィットするものであり、トランプ大統領からも歓迎されるものでしょう。
日本政府としても、トランプ政権と良好な関係を構築する手段として、日本が世界最大の対米投資国であること、トランプ的に言えば、日本が世界最大のMAGA支援国であることを強調すると考えられ、それは日本がトランプ関税の直接の標的となるリスクを低減させる可能性があります。
日米の経済関係を過度に悲観的に捉える必要はない理由は他にもあります。
トランプ外交の最重要課題は対中国であり、対中国でどこまで日本と協調できるかを探ってくると考えられます。
米国を唯一の同盟国とする日本にとって、米国との良好な関係は必要不可欠であることから、日本政府としても中国を挑発することは控えつつも、日本との関係は安全保障、経済の両側面で対中国に繋がるという点をトランプ大統領に提示することが考えられます。
トランプ大統領が、対中国で日本は信頼できる国家と位置付ければ、同様に日本がトランプ関税の直接の標的となるリスクの低減に繋がり、日米の経済関係が不安定化する可能性も低くなるでしょう。
一方、中国はトランプ大統領の保護貿易主義こそ自由貿易に対する脅威と強調することで、対日姿勢を軟化させているように映ります。
実際、中国はバイデン政権による買収阻止について、政治的考慮が経済合理性を上回り、国家安全保障の概念を拡大解釈した保護主義の一環だと表現し、米国の覇権的地位を脅かすいかなる企業や国家も米国の標的になり、同盟国であっても免れないとしました。
近年、日本企業の間では脱中国依存の動きが広がっていますが、日本企業の一部からは、米国の保護主義と中国の対日姿勢軟化により、脱中国依存の動きが収まるのではないかという声も聞かれます。
しかし、尖閣や台湾など日中間の地政学上の潜在的リスクは何も改善の方向に動いておらず、日本企業の中国回帰のような動きは、トランプ政権の対日警戒論の向上に繋がる可能性もあります。中国か米国かいう議論は好ましくありませんが、米中間の問題は日本企業にとって難しい問題であることは間違いありません。